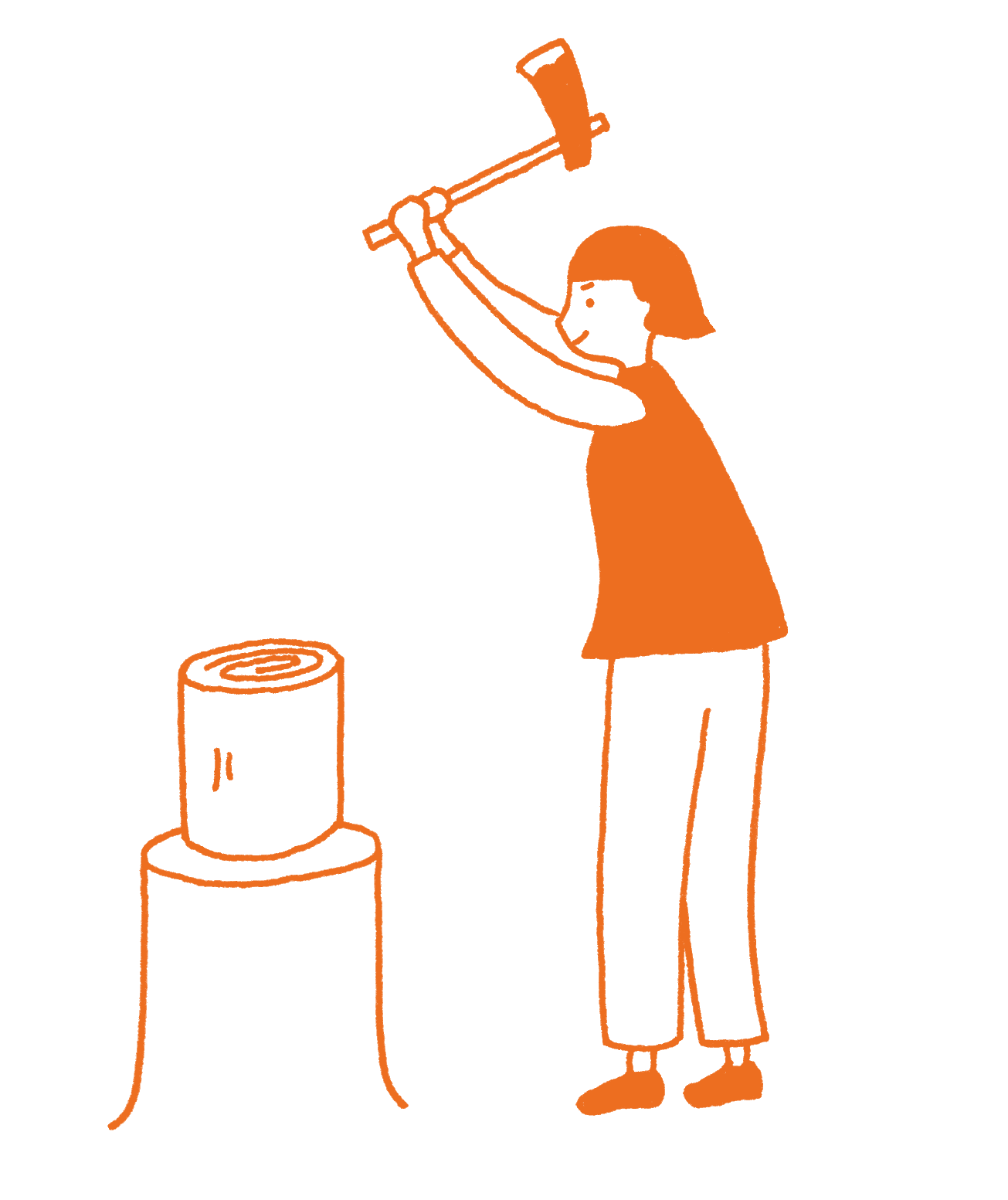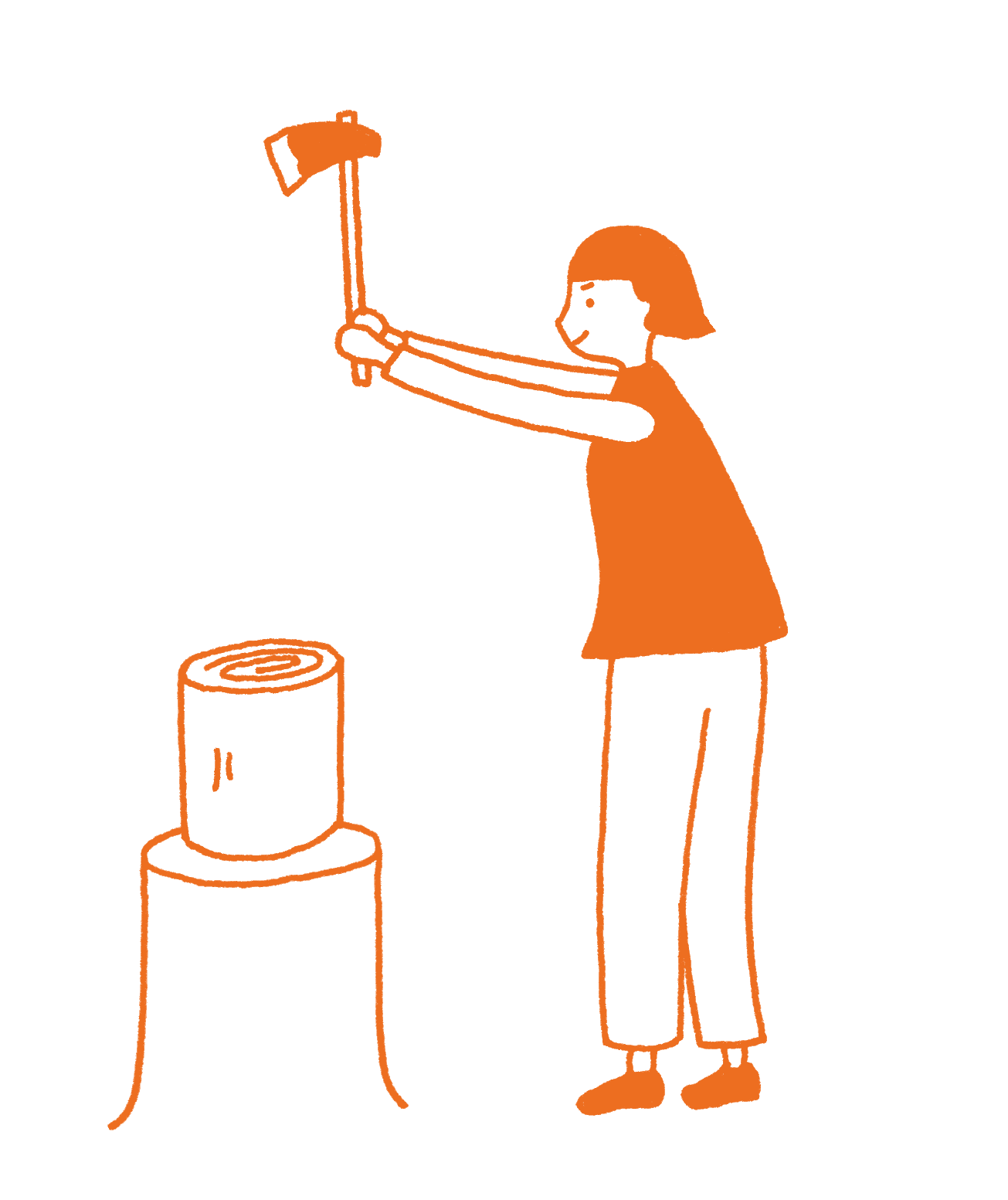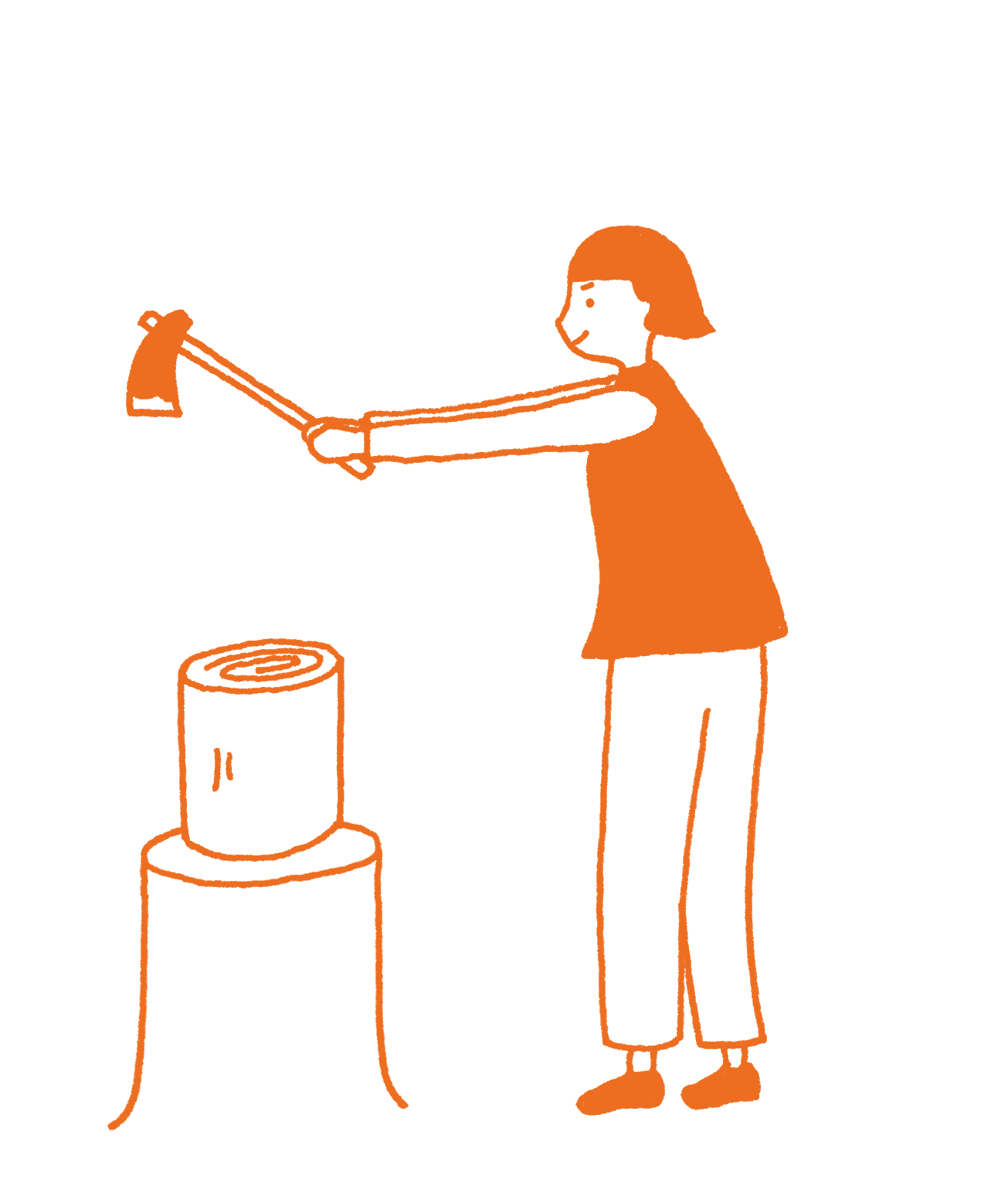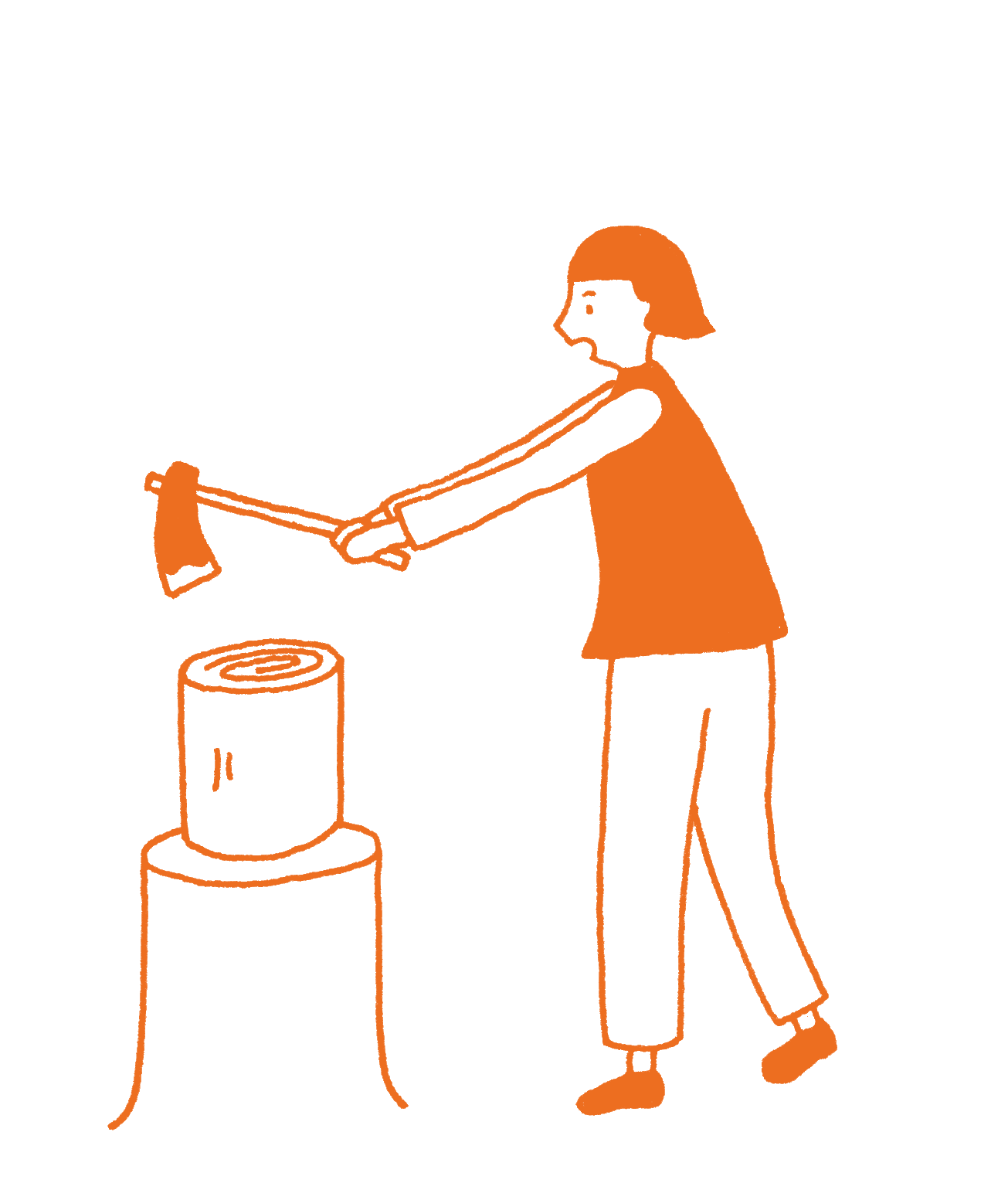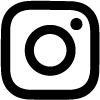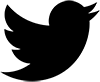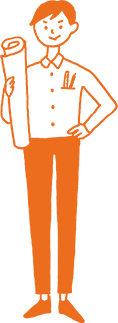皆様、こんにちは。今回のコラムは連載最終回「後編」です。
ここまで紀伊半島で製材所や森づくりの場を訪問し、その体験談を綴ってきました。
思い起こせば、2020年7月7日に「雇われ編集長の生涯学習」としてコラムがスタートしてからちょうど5年となりました。これは大きな節目です。
当時、キノマチプロジェクト立ち上げの頃、僕たちの活動の求心力にもなり得るコンセプトの打ち出し方が議論されていて、社内外の関係者と共に森林グランドサイクルの明確な定義(言語化):「森林資源と地域経済の持続可能な好循環」やロゴを定めました。

また、このロゴの意味合いについての語り口も考えました。僕たちとしては森林グランドサイクルは循環しているのでどこも起点になり得るのですが、左側の「木のイノベーション」すなわち、コンクリートや耐火被覆鉄骨と同等の耐火性能を有する木造構造材の開発が僕たちの活動としての起点(イメージ)でした。
その活用によって循環図の上部の「木のまちづくり」が可能となり、その木材需要が図の右側、木の需要拡大を伴う木を活用した用途変更プロジェクトやバイオマス発電などの「木の産業創出」をもたらし、その資金や人的資源が元となって下部の「持続可能な森づくり」投資を生み出します。
全体として森林資源と地域経済が持続可能に好循環していく。というコンセプトでした。
これをここでは仮に森林グランドサイクル1.0と名付けることとします。
この森林グランドサイクル1.0のコンセプトは不変と言えますが、ミートアップを経て、意味合いにおいて1.0では表立って見えていない、追加で言語化すべきいつかの要素があることに気づきました。
今回の視察では、北海道大学 和歌山研究林の麓にある平井集落には100年前に里山文化とも言えるキノマチが確実に存在していたことがわかりました。森林グランドサイクルで言えば、「木のまちづくり」が実現していたことになります。
しかし、今残るのは、廃屋になった古民家や使われなくなった水路跡といった遺構です。



遺構、廃屋といったハードは残っていますが、生命感が漂ってきません。もともとあったキノマチ(まちと森が生かしあう関係が成立した地域社会)感が失われています。どうしてか?
今回、実感したのはコミュニティの衰退がマチの活性化を止めた、の仮説です。いったい、コミュニティは何故、衰退したのか?
それはまた林業という森林産業が経済社会実態から遅れを取ったことの結果と言えそうで、要因と結果がぐるぐると循環してしまいますが、コミュニティあってこそのマチの発展とは言えそうです。「マチ」にはその地域に密着するコミュニティの存在が欠かせないということです。
やはり木に関わるコミュニティの再生は欠くことができません。これ以降、(仮)森林グランドサイクル1.0の構成要素に(仮)同 2.0として加える新要素を&で追記することにしてみます。
「木のまちづくり」→「木のまちづくり&木に関わるコミュニティの再生」
次の「森の産業創出」では、産業だけでなく、心地よさ、楽しみ、自然との触れ合い、と言った人々のウェルビーイング(well-being)や生命力と切り離しては成り立たないことが、見えました。
この100年、僕たちはひたすら画一的な人工物で自分の周辺を周辺環境と切り離してきましたが、本来は自然、建築、人間は一体的に繋がっていて、森林空間やキノマチに身を置くことで人間本来の心地よさ、楽しさ、も獲得することができます。
つまり、機械的な言葉の響きのある、「産業」だけでなく、そんな自然との調和によって心が深く呼吸するようなウェルビーイングの再獲得も目指したい。

「森の産業創出」→「森の産業創出&森林によるウェルビーイングの再獲得」
次の「持続可能な森づくり」において「木」の健全化にはその生態系や土壌といった土台の上にこそ成り立ちます。今回の北海道大学 和歌山研究林では天然の広葉樹林の空間に身を置くことができましたが、光が差し、風が通り、水が流れ、時にそれらが滞留する空間は生物の宝庫であり、循環する生態系を維持することが持続可能な森に繋がっていることを痛感しました。

同時に人にとっても快適で心地よい空間であったことは言うまでもありません。 土台となる豊かな生態系なしに、持続可能な森林は生まれません。
「持続可能な森づくり」→「持続可能な森づくり&豊かな生態系の再構築」
さて、ここまで書いて気づいたのですが、今回のミートアップを経て加えたい要素は僕たちが「元来、持っていた状態への回帰」の意味合いが強い、ということです。
すなわち、木に関わるコミュニティの再生、森林によるウェルビーイングの再獲得、持続可能な生態系の再構築。多分、これらは全て元来、僕たちの祖先が長い間、過ごしていた身近な周辺環境とも言えるのではないでしょうか。
しかし、世の中の近代化に伴って急速に失われました。森林グランドサイクル2.0で加えるべきはその失ってきたことを自らが自分の身のまわりから取り戻し、できれは加速したいということの表明なのではないでしょうか。
一度、切れたサプライチェーンと近代化への慣性力はそう簡単に元に戻りません。そのために最後の「木のイノベーション」が推進エンジンとして必要になってきます。ではキノマチウェブ5年間を経た今、その「木のイノベーション」には変化が必要なのでしょうか。
そうです。これまでこのイノベーションは主に新築高層化を対象とした耐火木造に関わることでした。
そしてこの10年ほどで耐火木造技術は事務所、学校、商業施設、スポーツ施設などあらゆる建築種別に展開されるようになり、加えて、規模的にも3時間耐火が必要な100メートル超えの建築も計画されるなど、かなり成熟してしまいました。
世の中的にはまだまだ認知度は低いですが、高層耐火木造を目指して木に関わってきた僕たちのような関係者には都市木造建築がその黎明期から普及期に入った意識が生まれている気がします。キノマチウェブ記事でも通常の木造建築では記事内容に新規性が弱まってきたことも実感しています。
したがって、さらに社会認知を得るために、これからは大規模な耐火木造だけではなく、今回のキノマチミートアップで新たに見えてきた、木に関わるコミュニティの再生、森林によるウェルビーイングの再獲得、持続可能な生態系の再構築を強く意識する必要がありそうです。
そしてそこにイノベーションを起こすために快適性、健康寄与度、色彩感覚を含めた意匠性、維持管理を踏まえた耐久性、サーキュラーを前提とした部材構成、分離・交換性などの分野での新しい技術が必要になってきます。
僕が所属する総合建設業はそれらの開発や適用を生業にしているので森林グランドサイクル2.0としてさらに対象を広く、自分事にする必要がある。耐火性能以外の性能に焦点を多角化していくことでまだまだ木造展開の視界は広がり、キノマチウェブとしても社会に価値のあるHOTな情報を発信することができそうです。
キノマチプロジェクトの立ち上げから5年が経ち、森林グランドサイクルの川上から川下への循環が回り始めました。キノマチウェブではその状況を外部に発信し続けています。
しかし、当初の森林グランドサイクルの活動は成熟期を迎え、新たな視点が必要な段階になった。今回、ミートアップで議論や体験を重ねたことで近傍での木のコミュニティ再生、森林によるウェルビーイング再獲得、持続可能な生態系の再構築等の再活性化など、さらに活動領域を広げる必要性に気づきました。
これからは川上から川下分野の再活性化のために耐火木造以外のイノベーションにも取り組み、それを森林グランドサイクル2.0としてより広い世界観を持って発信していきます。
新築高層化のための木のイノベーション(耐火木造の開発)→ 再活性連鎖化のための木のイノベーション(耐火木造の開発 & 快適木造、美観木造、耐久木造、交換木造、標準木造の開発)
最後に、キノマチウェブにもそのインタビュー記事が掲載されている水戸市民会館の設計者である建築家、伊東豊雄さんは2025年4月1日発行の出版物「誰のために 何のために 建築をつくるのか(平凡社)」の中で次のように語っています。
「かつて人間は良い水を求めて川の畔に住み、太陽の光を浴び、新鮮な空気を吸収しながら暮らしていました。
定住生活を始めてからも、私達の住まいは強い太陽光を屋根や庇で遮断したり、我が国の住居では地面からの反射による柔らかな間接光として屋内に取り入れたり、涼風が室内や縁の下を通り抜ける工夫をするなど、自然と一体化した暮らしを建築にしてきました。
素材も木を中心とした自然素材でつくられ、つい最近まで「建築もまた自然の部分であった」のです。建築も自然の部分であったということは、建築も人体と同じく自然界の「流れ」と「淀み」を構成していたということに他なりません。それどころか人体を形成している自然の「流れ」と「淀み」をよりスムーズにするための装置であったと言えるでしょう」
自然も建築も人も同じ循環の中にいるのですね。
できれば次は森林グランドサイクル2.0の世界観の中でお会いしたいものです。

(語り手)キノマチウェブ編集長
樫村俊也 Toshiya Kashimura
東京都出身。一級建築士。技術士(建設部門、総合技術監理部門)。1983年竹中工務店入社。1984年より東京本店設計部にて50件以上の建築プロジェクト及び技術開発に関与。2014年設計本部設計企画部長、2015年広報部長、2019年経営企画室専門役、2020年木造・木質建築推進本部専門役を兼務。