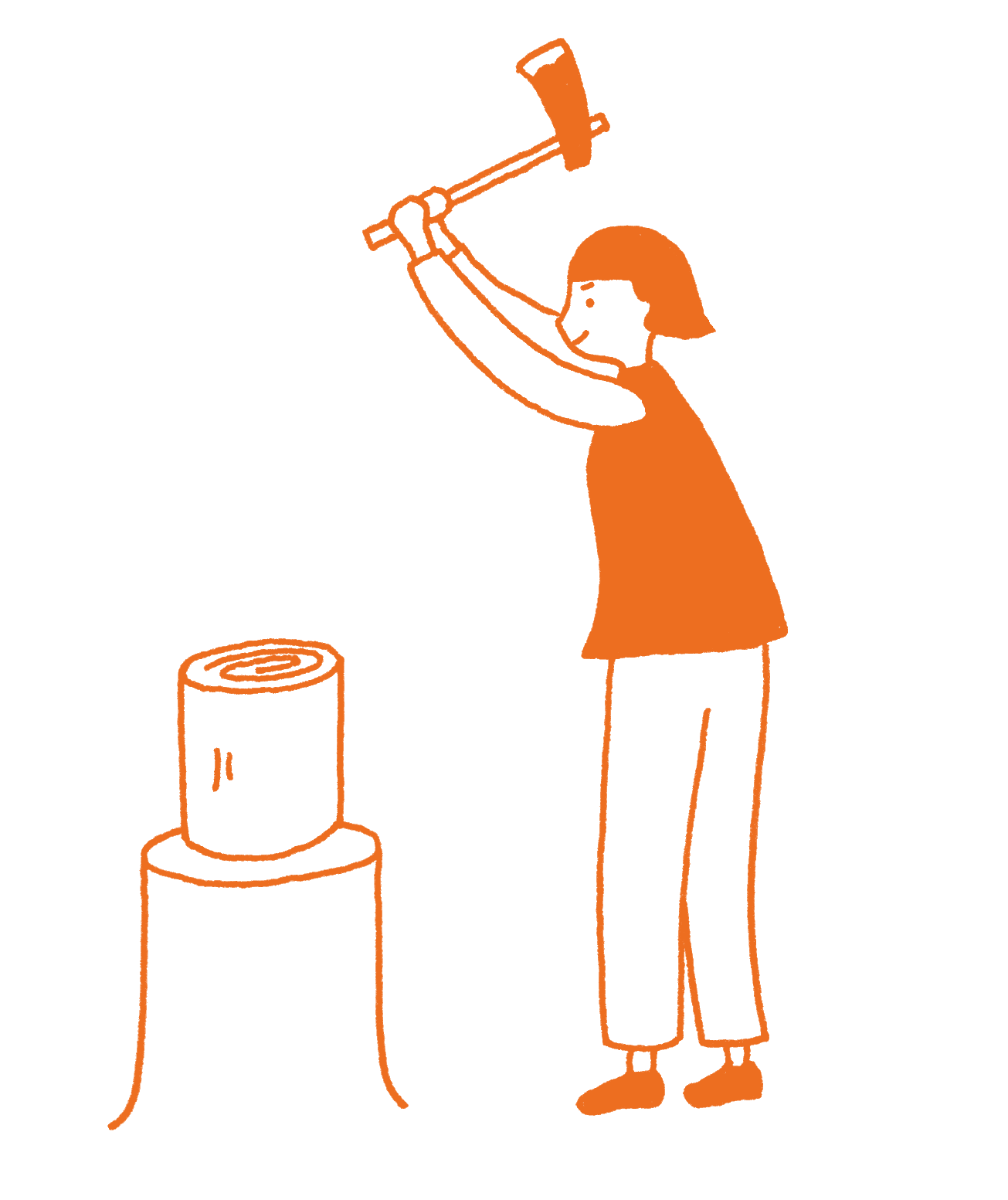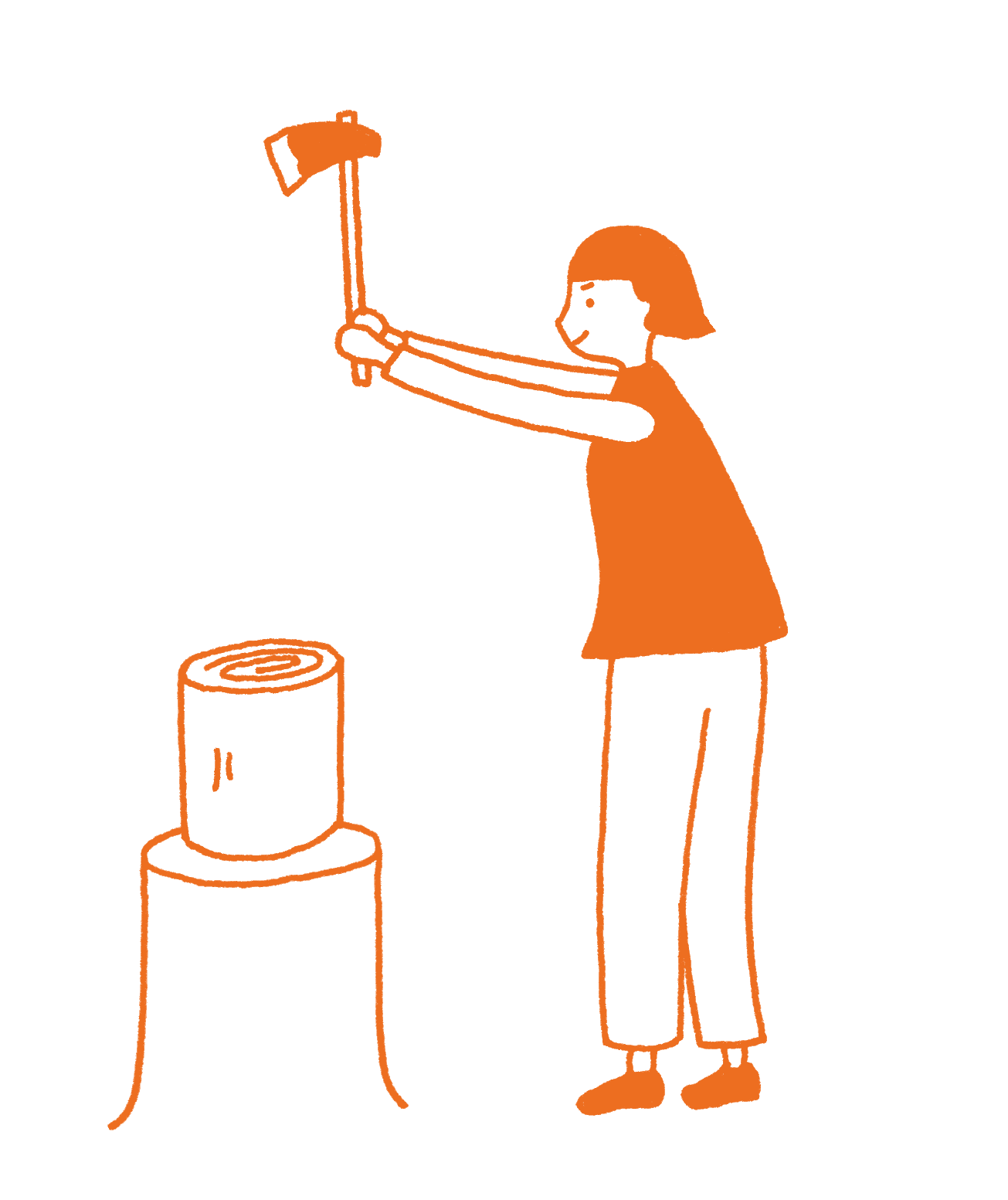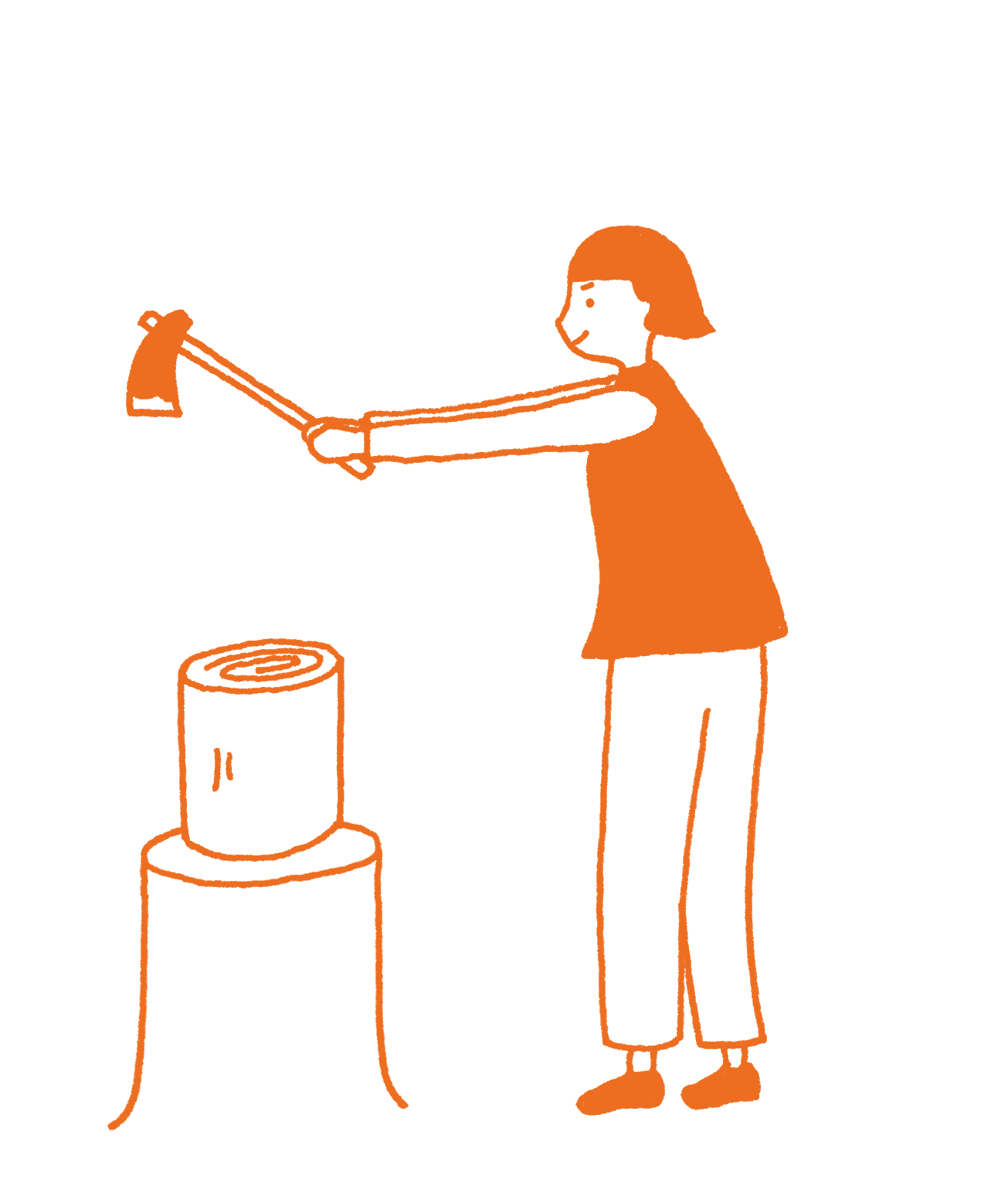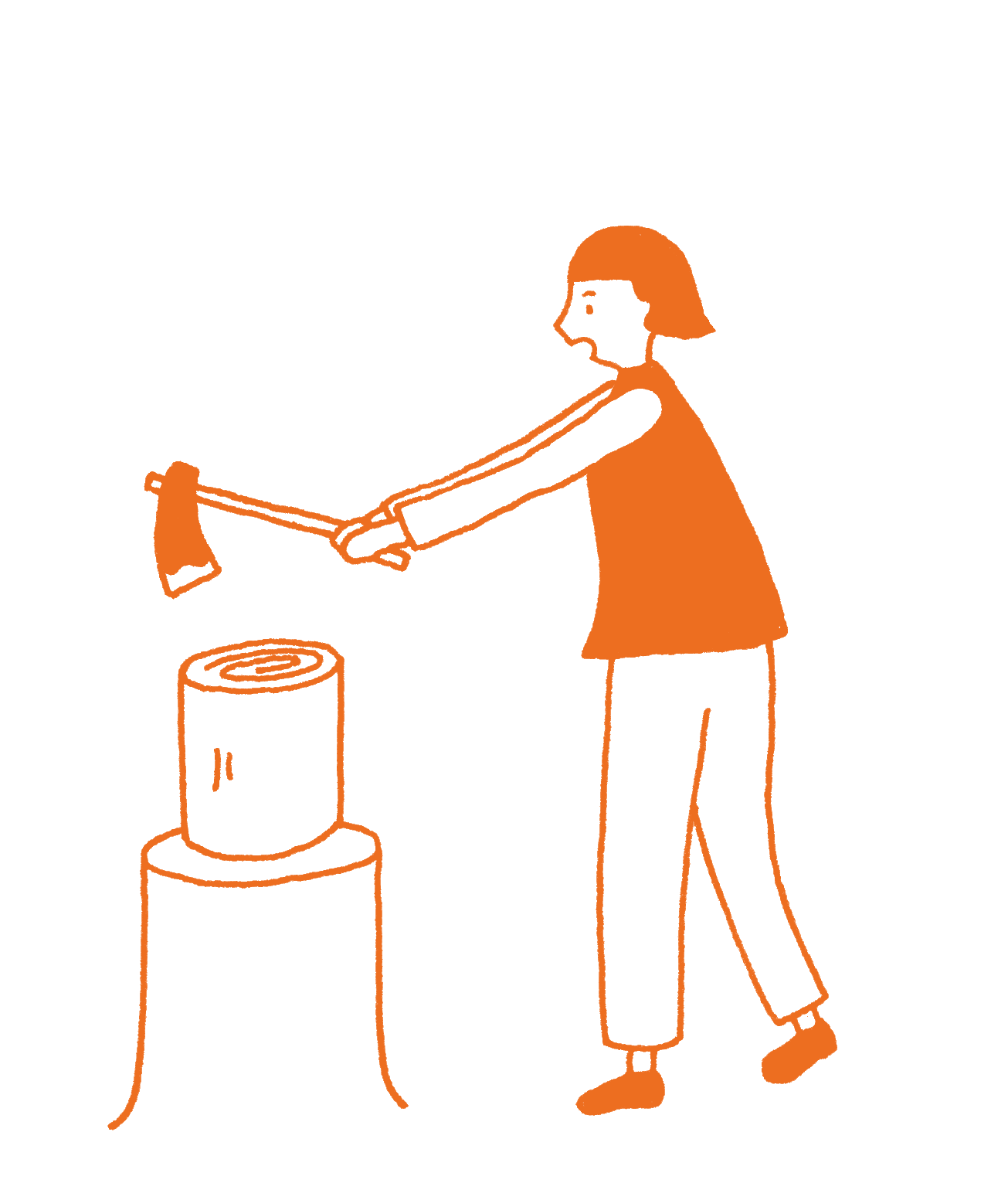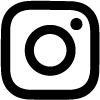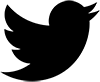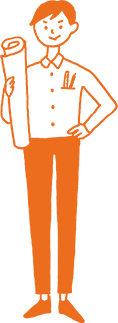「キノマチウェブ」は、木に関わる方々や、木に関わる暮らしに興味のある方々をつなげたいという想いから生まれた、木を題材の中心に置いたウェブマガジンです。そんなキノマチウェブは、竹中工務店で長年、建築プロジェクトに関わってきた“超現場志向”樫村編集長と、“元都会っ子”編集者のアサイアサミが、各業界のプロフェッショナルを巻き込みながらつくっています。そんなキノマチウェブの「中の人」はどんな思いを持ってキノマチウェブを編集しているのかをこのページでじっくりお伝えします。

(語り手)キノマチウェブ編集長
樫村俊也 Toshiya Kashimura
東京都出身。一級建築士。技術士(建設部門、総合技術監理部門)。1983年竹中工務店入社。1984年より東京本店設計部にて50件以上の建築プロジェクト及び技術開発に関与。2014年設計本部設計企画部長、2015年広報部長、2019年経営企画室専門役、2020年木造・木質建築推進本部専門役を兼務。

(聞き手)キノマチウェブ編集ディレクター
アサイアサミ Asami Asai
東京都出身。大学在学中、宝島社入社。雑誌編集者を経てタワーレコードのフリーペーパー「TOWER」の編集長を5年間務める。その後フリーランスを経て、2012年岡山県へ移住し、広告会社ココホレジャパンを設立。移住情報誌TURNS副編集長などを歴任し、地方地域、環境問題、ライフスタイルなどのジャンルを得意とする編集者として田舎で楽しく暮らしています。
木造木質建築の可能性を予感させた長野市オリンピック記念アリーナ「エムウェーブ」
――樫村さんは、ものづくりをする技術者として、大小さまざまな建築プロジェクトの現場に携わってらっしゃったのですよね。
樫村 竹中工務店では37年間勤務し、キャリア前半の1999年までは、設計部でエンジニアとして数多くの建築プロジェクトに携わってきました。しかし、その間で残念ながら木造をつくったことはありません。
私が技術者としてプロジェクトに関わっていた当時は「超高層」「大規模ドーム」など、大きいものをいかに合理的に建設するかが最優先課題で、木には意識が向かいませんでした。そのキャリアのなかで、今でも木を使った建物といえば、1990年後半の「長野オリンピック1998」のメインアリーナのコンペを思い出します。当社は開閉式のドームを提案したのですが、最優秀は、屋根架構に木を使った他社の案でした。その案では、屋根に地元長野産のカラマツを使ったことが審査において大きな加点になったと聞いています。
――90年代後半、「地産地消」の考えかたは一般的ではなかったように思います。建材持つのストーリーが決めてのひとつになるなんてびっくりしましたね。
樫村 そうですね。でも考えてみれば、木は自然材料で環境に優しく、また地域経済に果たす役割が大きい。すなわち「木の文化」を広げていくことが、士気も上がり、地域にとって重要な要素と考えられたのだと思います。
なぜ、いま木造建築が注目されているのか
樫村 もともと木は、日本の生活の中心を占めていましたよね。薪、家、家具、椅子など、生活の基盤に木がありました。それが、戦後、工業化ともにエネルギーは石油や石炭、建築資材は鉄やコンクリートに取って代わられます。また市街地の大規模な建物や不特定多数の人々が集まる建築においては、耐火性能の確保がネックになっていました。
――日本は、関東大震災や太平洋戦争を経て「燃える」ことは耐え難いこととして、耐火基準を厳しく設定し、長い間、公共建築を鉄筋コンクリートや鉄骨に耐火被覆を施して建物をつくりました。しかし、建築基準法の性能規定化や耐火に関する技術開発が進み、木の建物が増えてきた気がします。
樫村 建物を建てるお客さまも含め、感性に訴える木造・木質空間の良さへの注目度が高まってきているように感じます。オフィスや商業施設に留まらず、病院、学校、駅舎など、いろいろな建物に木が適用されています。まさに「木の復権」です。

――需要が増えることで、木のイノベーションもまた起こりそうです。
実績が進むにつれて、いろいろな材料が使われるとバリエーションが増えます。例えば、材料的に均一でない、節がある、ねじれている、また、材種で色合いが異なる、などの自然素材ならではの特性をさらに生かし、新しいデザインへの展開も期待できる、木も次のステージにいければと思っています。

キノマチウェブの使命は川上・川中・川下をつなげること
――「キノマチウェブ」をローンチした背景には「森林グランドサイクル®」にもあるよう自然と経済が両立したまちへの取り組みもあります。
樫村 「森林グランドサイクル」というメカニズムが持続的に働いていることが必要だと考えています。それを実践するコミュニティづくりのためのメディアがキノマチウェブです。
林業や製材業に関して林業や木材業界は、戦後、さまざまな要因で需要が減り、流通も滞ってしまいました。70年以上も停滞していると、モノだけでなく、ヒトや情報も分断が起こってきます。
サプライチェーン生産者(川上)、加工や製材者(川中)、最終製造・エンドユーザー(川下)の三者間でマーケティングやコミュニケーションが成立しなくなります。それを改めてキノマチウェブで呼び起こしていきたいと考えます

――また、新型コロナウイルスの脅威は、わたしたちに「生活環境」と「経済活動」を以前よりも深く考えるきっかけをつくったともいえます。キノマチウェブでは、いま、どんなことをみなさんに伝えるべきだと考えますか?
樫村 「いま」とアサイさんはおっしゃられますが、この「いま」というのが非常に大きなポイントだと思っています。それは経済循環としてのヒト・モノ・情報の流れが一瞬にして変わったのがまさに「いま」だからです。
いま、人とモノの流れが止まっても、情報だけは滞ることなく、扱う量と機会が加速度的に増加しています。
たとえば、家でテレワークをするならば、気持ちのよい自然を取り込みたい。密閉を避けるのなら、自然素材を使う風通しのよい和的な建築が整合するので木造木質に向かうのは自然な流れです。

木造や木質が、オープンで自然と共生できる「居心地のいい過ごし場所」として求められていくと思います。
――コロナウイルスの脅威が、自宅にこれまでよりもはるかに長い時間、自宅に留まることを要請し、それが生活の場を見直すことになり、自らの環境を整えることに立ち返るきっかけになるかもしれないということですね。
樫村 自宅で過ごす時間に比例して、内装や仕上げ材と接する時間も長くなるわけです。例えば、テーブルは無垢材を使ってみたくなるかも知れない。すると木に関する実践的で信頼性のある情報が必要になるはずで、それに応えられる情報を提供できるキノマチウェブでありたいと思っています。

そのように新たな生活様式で加速されるであろう、木の効用に、人々が気づくようになれば、木の活用は加速され、新しい生活様式にカスタマイズや個性的という付加価値も加わって“木の復権”という我々が考える社会課題の解決に繋がるだろうと考えています。
――そんな樫村さんが、個人的に取材したい案件があったら教えて下さい。行きたい場所も!
樫村 改めて「木」を考え直してみると、広報部時代、当社の広報誌「approach」の取材で訪問したアメリカ西海岸サンタモニカにあるイームズ・ハウスをもう一度訪れたいですね。
1949年建設の構造体は、鉄とガラスによるイームズ夫妻の自宅兼事務所として有名ですが、内装やインテリアにはタローウッド材や低木、また木製を含めたイームズ・チェアなどの家具が内包されている。また建物に平行して群生しているユーカリの木々が、建物のファサードと室内に緩やかな影を落とします。
イームズ・ハウスは夏場に極めて降水量が少なく、毎日晴天つづきで日差しが強烈なカリフォルニアにあって木々が陰影となり、住む人に安らぎや自然との共生の必要性を訴え、また訪問者に鳥のさえずりや木々の揺らぎを与える住宅兼オフィスです。
2011年から文化遺産として後世に残すため米国のゲッティ財団の協力を得て「250年プロジェクト」と称するメンテナンス計画を進めています。
それについて、イームズ夫妻の孫、ルシア・アートウッドさんは「250年には長期的な視野での修復を行うという意味合いを込めていて、敷地に生えているユーカリの樹にちなんでその名をつけました。ユーカリの樹は種類によっては、寿命が250年を超えると言われています。イームズ・ハウスが250年後もまだ残っていれば、家が抱えていたメンテナンス上の重大な課題に全て対応できたことを意味します」と話していたことが強く印象に残っています。
さらにイームズ・ハウスは住宅とオフィスの機能を持ちながら、チャップリンなどを招いたお茶会も開かれるなど、来客へのおもてなしに際して部屋の使いかたに柔軟性をもたせている点でも極めて日本的です。今、もう一度、訪問したいです。
――キノマチウェブの使命、というと大げさですが、どんなことを担える存在になればいいとお考えになりますか?
樫村 キノマチウェブの目標が木に関わっていくプレイヤー相互の橋渡しなので、読み手が新たな木の価値をわかってくださればいいと思っています。
「扱っている木がどういうものか」「どんな価値を生むのか」「背景情報や生産者の想い」を示す必要があります。また、逆の流れとして最終製作物の設計者やエンドユーザー(川下)のニーズを川上の林業側に届けることも有効で、それが川上(生産者)と川下(最終製作者、使用者)の双方向コミュニケーションだと考えています。
――コミュニケーションを増やして、キノマチプロジェクトの仲間もたくさん増やしていきたいですね。そのためにも川上・川中・川下をつなぐグッドニュースをどんぶらこっこと届ける、川の流れのようなメディアに育てていきましょう!