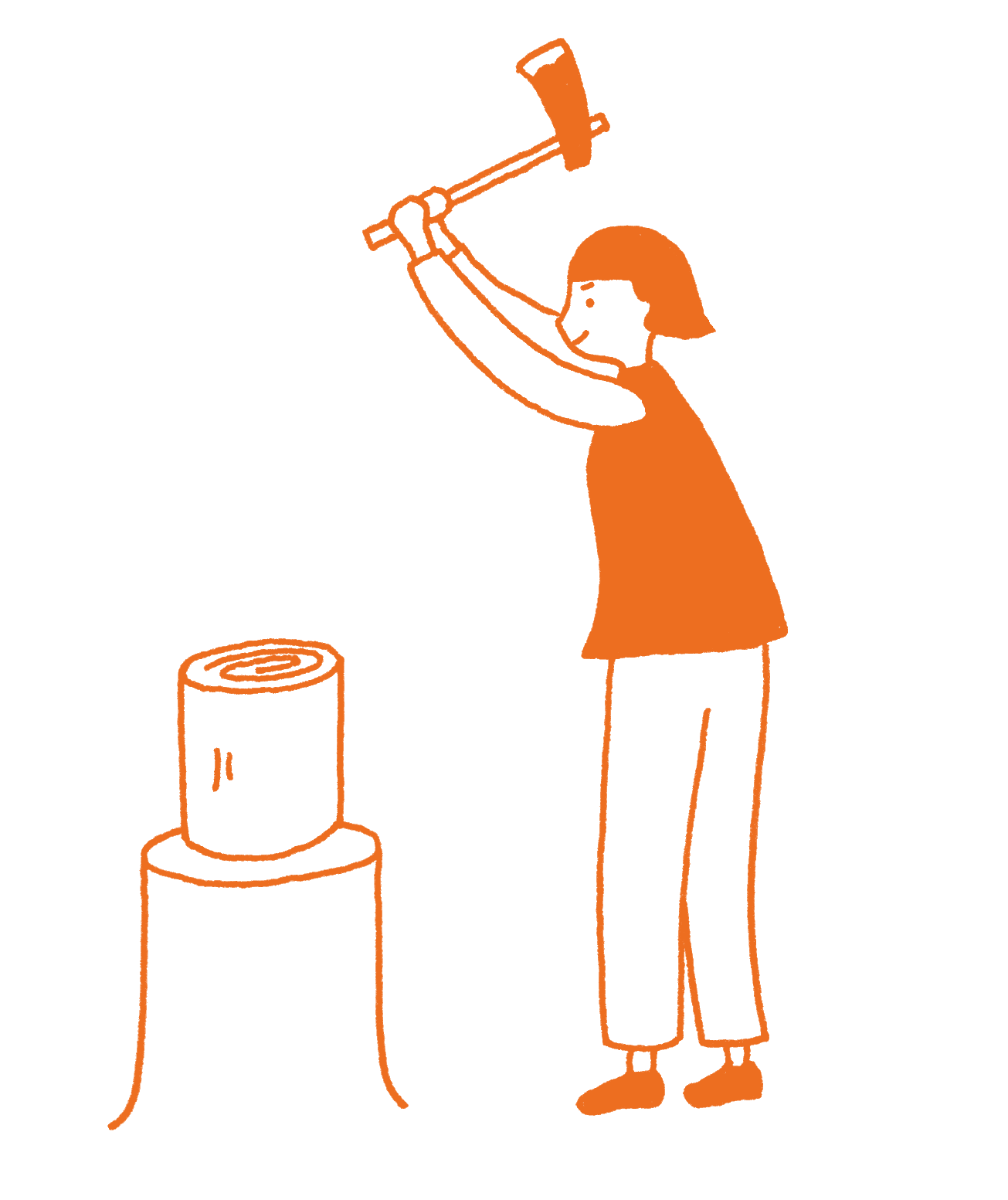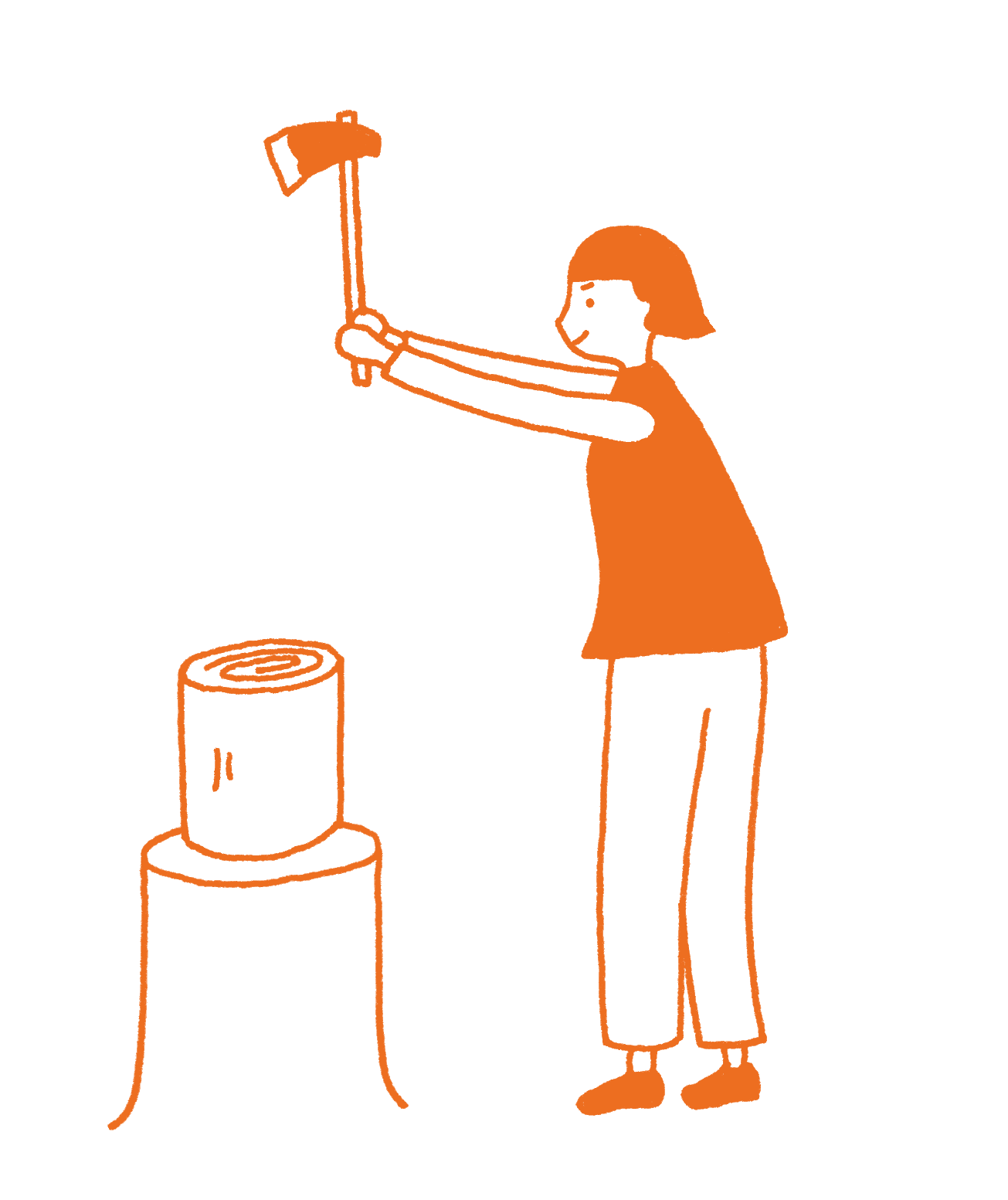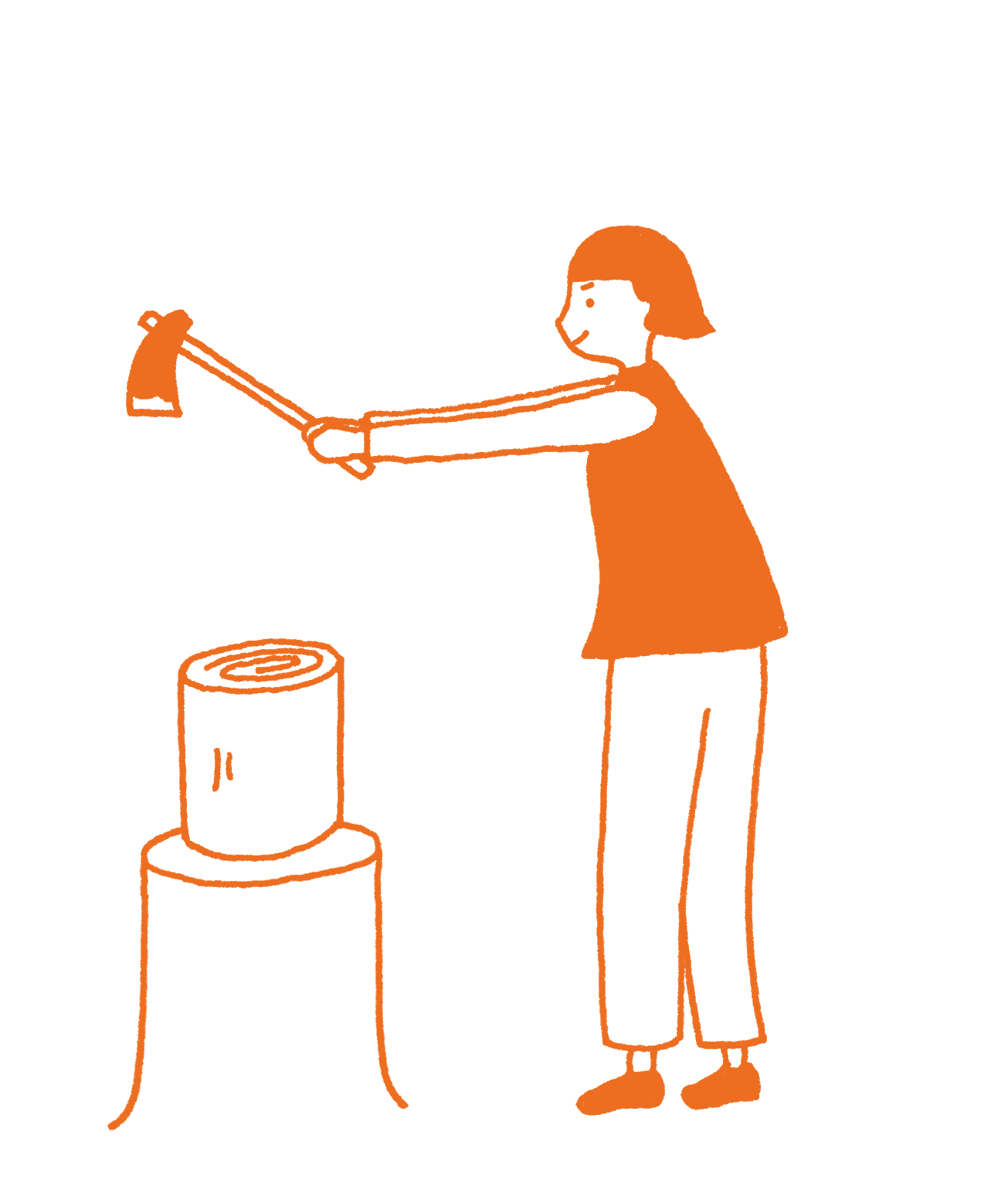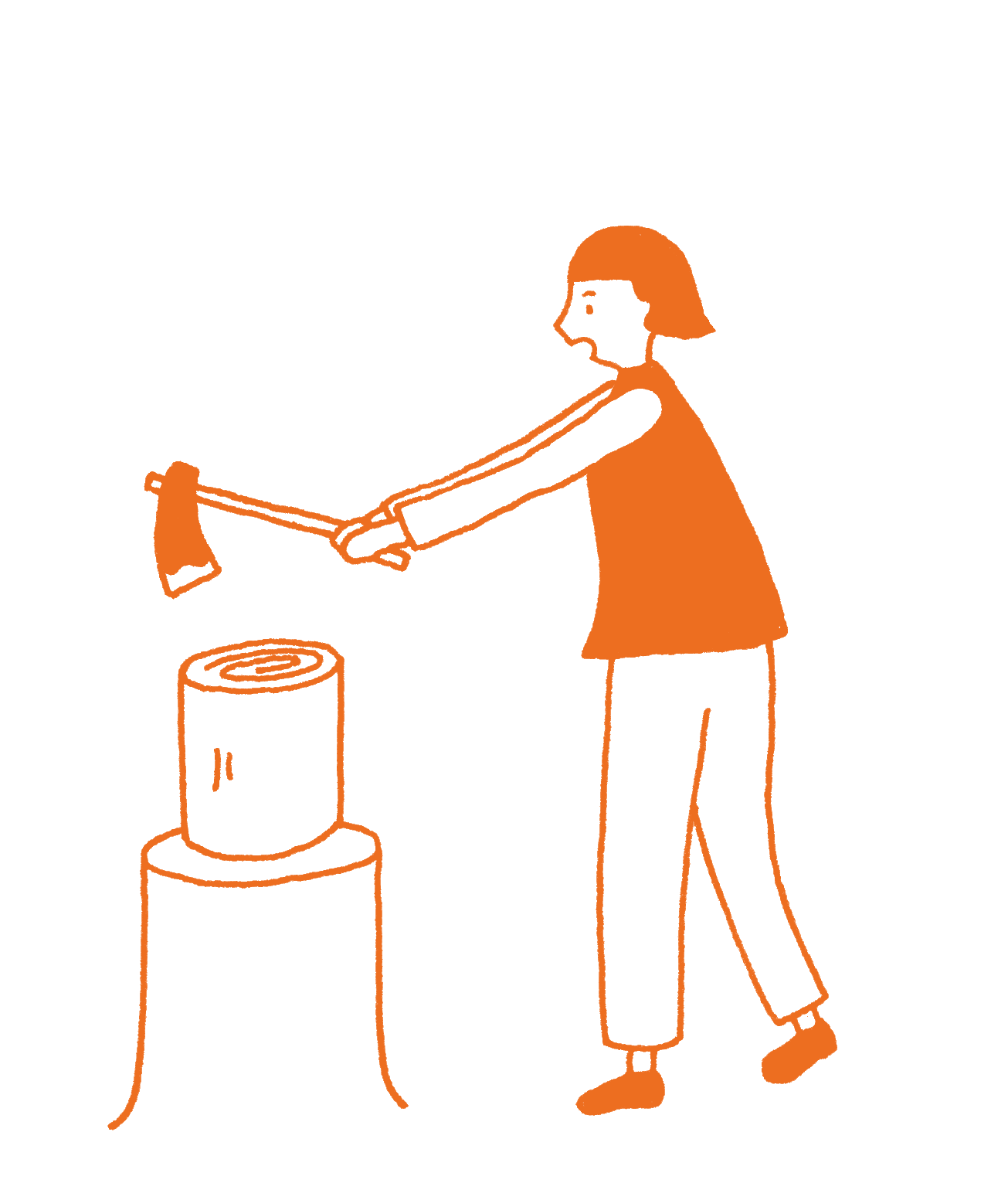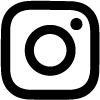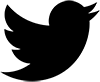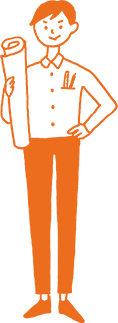こんにちは。2023年に入って早くも4か月が経ちました。昨年のキノマチ活動を振り返ってみると僕には『北海道地区 FMセンター』(以下北海道FMC)のプロジェクトが印象的でした。
その理由を辿ってみると、2つの特徴が思い浮かびます。
小回りな森林グランドサイクル
ひとつは建物の規模が比較的小規模なこともあり、約1年間で森林グランドサイクル®を回したことです。
すなわち、下図の左下
「ダブルティンバー:木のイノベーション」を起点にして、 「北海道FMC:木のまちづくり」が竣工し、その過程で
「道産木(カラマツ)の地産地消:木の産業創出」に繋がり、 さらには「トドマツを植林する:持続可能な森づくり」といった一連の活動を実践し、メディアを通じて発信するまで短期間のプロジェクトであったこと。

北海道キノマチコミュニティ
2つめの理由として、多様な木のプレイヤー達との協働が挙げられます。
竹中工務店の北海道支店の人々を取り巻く、産・官・学の木のプレイヤー達が素晴らしいコミュニティを形成しています。みなさんのキノマチ活動はとても献身的で頭が下がります。
その活動に報いるためにも極力、現場に足を運び、現実を幅広く発信することが編集長の使命だと感じています。このプロジェクトに関係者が賭ける想いはキノマチウェブの記事やキノマチ公式YouTubeチャンネルの「オンライン見学会・討論会の動画記録」で配信されていますので是非、覗いてみてください。 北海道の森林とまちの未来を語る【オンライン見学会編】ダイジェスト版
北海道の森林とまちの未来を語る【トークセッション編】ダイジェスト版
さて、たびたび感じるのですが、僕が所属する総合建設業は森林サプライチェーンの川下産業であり、都市での活動が中心でどうして木造木質資材を都市に持ってきて組み立てる、「都市に第二の森林を!」を意識しがちです。
しかしながら、当然、逆の「森林に人を!」もキノマチ活動であるはずです。山に若い人や子供達に山に入ってもらって何らか木に関連したアクティビティを行ってもらう。さらには森の中で居場所を創ってそこで過ごしてもらう。山で過ごす関係人口をもっと増やすことを中高層都市木造の実現とバランスさせることを忘れるわけにはいきません。
ということで今回のコラムは、サクセスストーリーともいえる北海道森林グランドサイクル実践例に関連して、北海道のとある森林に、製材関係者などと共に入り、そこで実施した製材作業のお話です。
sizedown-1024x768.jpg)
山間部での製材活動
この森林はトドマツやシラカバが主体となっています。
広大な敷地の山林道をしばらく進んでいくと、ところどころでトドマツの原木の土場が目につくようになります。
その後、道幅が広がり、緑色のテントが張られた伐採用バックホーと簡易製材機(Wood Mizer)が稼働している平坦地に到着しました。ここが、今回、製材をする作業場です。

今回、山間部での製材は、廃材をその場に残し、必要な部材だけを運ぶ「物流の軽減」が主目的とのこと。今回の入山に加え、山側で製材する計画・実施・指導は森のエバンジェリスト(と僕が勝手に思っている)outwoodsの足立さんとその仲間達が主導してくれました。足立さんには先ほど話をしたYouTubeにアップした北海道FMCのオンライン討論会にも参加いただいています。
製材機は必要な精度を保って据え付けられ、トドマツの製材はすでに始まっていました。ここに至るまで、天候にも影響される山間部に必要な重機を運び、水平精度の調整の上、組み立てるなどの準備には大変な労力がかかっただろうと思います。

周到な準備のお蔭で、当日はトドマツを製材機にセットし、電源を入れてゆっくりと門型の柱を推し進めるだけで、住宅用床材が出来上がっていきます。
今回の30ミリメートルの床用ラミナ製材の作業はほとんど自動化されていて特殊な技能は不要な作業に思えました。段取り(と片付け)90パーセント、加工10パーセントという印象でしょうか。
とはいえ、バックホーの操作も製材機の刃の入れ替えや操作指導も全て足立さんとその仲間達頼みです。献身的な先導者のありがたさが身に沁みます。

-1024x768.jpg)
現地に9時半頃入り、昼食を挟んで13時半くらいまで、床用ラミナを製作していていましたが、それと並行して子どもたちは斧で木を割る薪割り体験で大変な盛り上がりを見せていました。そんな非日常的な体験が、将来、彼ら子どもたちと山の距離感を縮めてくれたらいいなあ、と思って眺めていました。
僕も薪割りを試したのですが、スパッと割るには思い切りの良さと体力が要ります。斧が途中で止まってしまい、納得がいくまで何度もトライが必要になります。

sizedown-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
さらに家具の天板などに使う栗の木を製材することになりましたが、ごつくて曲がっている栗の丸太を形状のまま板にしました。曲がっているのがその木の個性、特有の味でもあります。
僕もトライしました。途中で足立さんがカッターの刃を取り換えてくれたので切れ味は抜群でいたってスムーズな作業でした。
こんな体験も北海道の素敵なコミュニティがあってからこそ可能です。やはり専門性の高い先導者、翻訳者、コンシェルジェの参画はこのような活動の展開に必須ですよね。

作業場を離れて山林道を散策すると、誰かが「シマエナガが飛んでいる!」と叫びました。遠くてその姿をはっきりとは拝むことはできませんでしたが、どうやら北海道に生息する「雪の妖精」と呼ばれている小鳥のようです 。
この辺りが生息地とはいえ、多数のシマエナガを目撃できるのは稀とのこと。ありがたい。こういう偶発性も森林アクティビティの楽しさ、魅力の一つですね。この時ばかりは入山から5時間以上過ごして滲みてきた寒さが吹っ飛びました。
木のプレイヤー達との協働体験、今回も北海道からでしたが、日本には多様な森林と気候風土があります。森林との関係人口が増えることに期待して各地の森林や里山からもいろんな情報を届けたいと思います。

(語り手)キノマチウェブ編集長
樫村俊也 Toshiya Kashimura
東京都出身。一級建築士。技術士(建設部門、総合技術監理部門)。1983年竹中工務店入社。1984年より東京本店設計部にて50件以上の建築プロジェクト及び技術開発に関与。2014年設計本部設計企画部長、2015年広報部長、2019年経営企画室専門役、2020年木造・木質建築推進本部専門役を兼務。