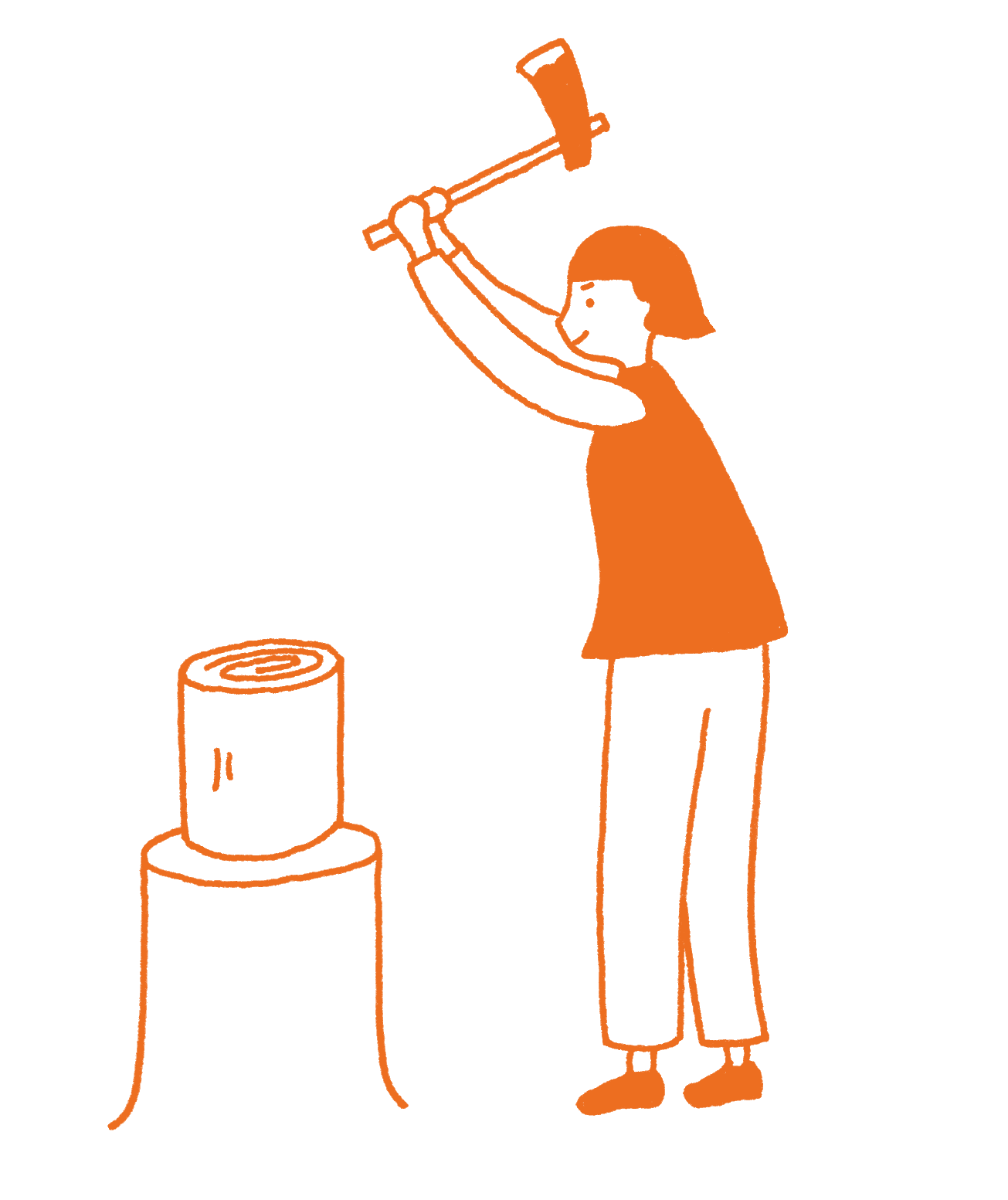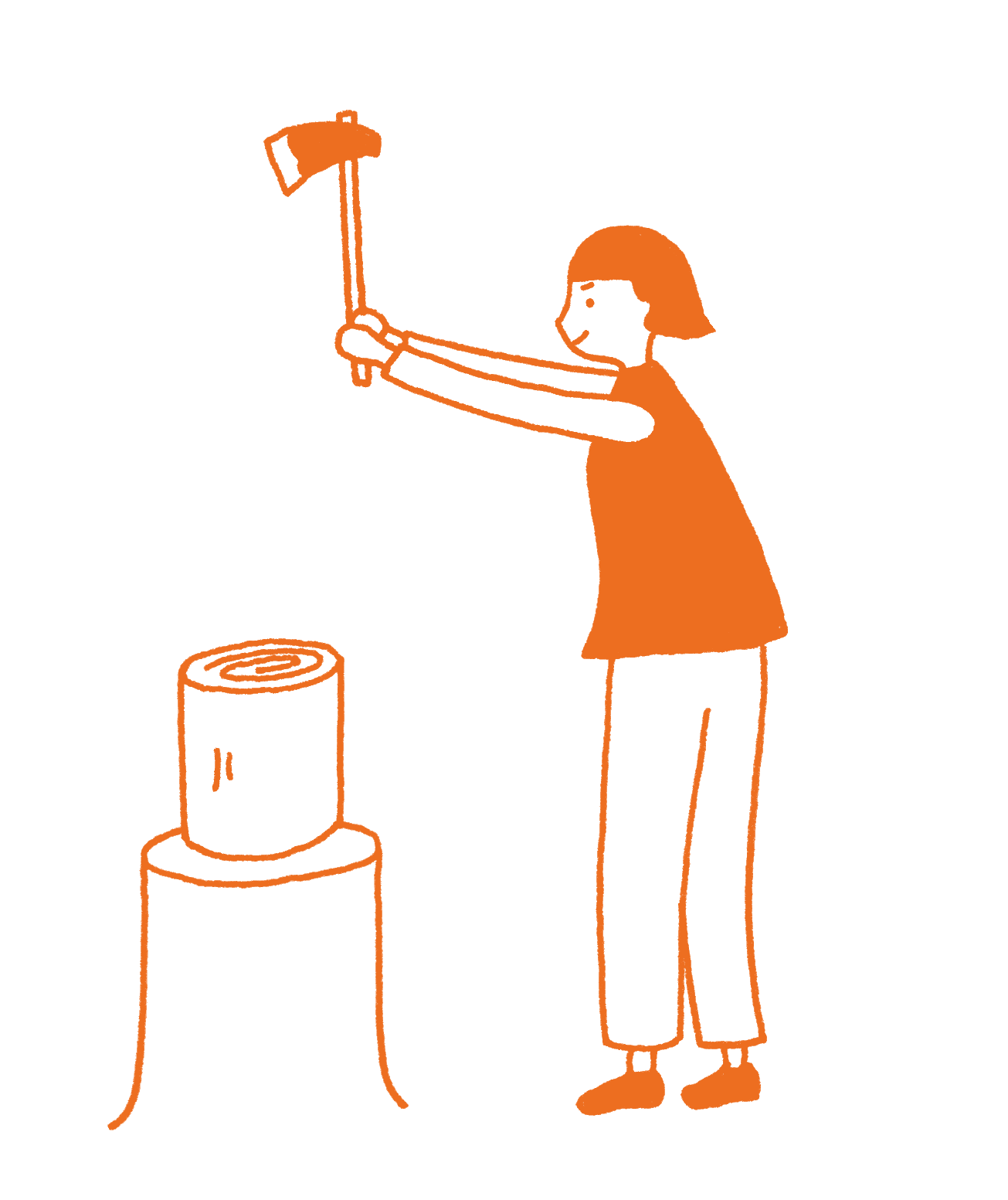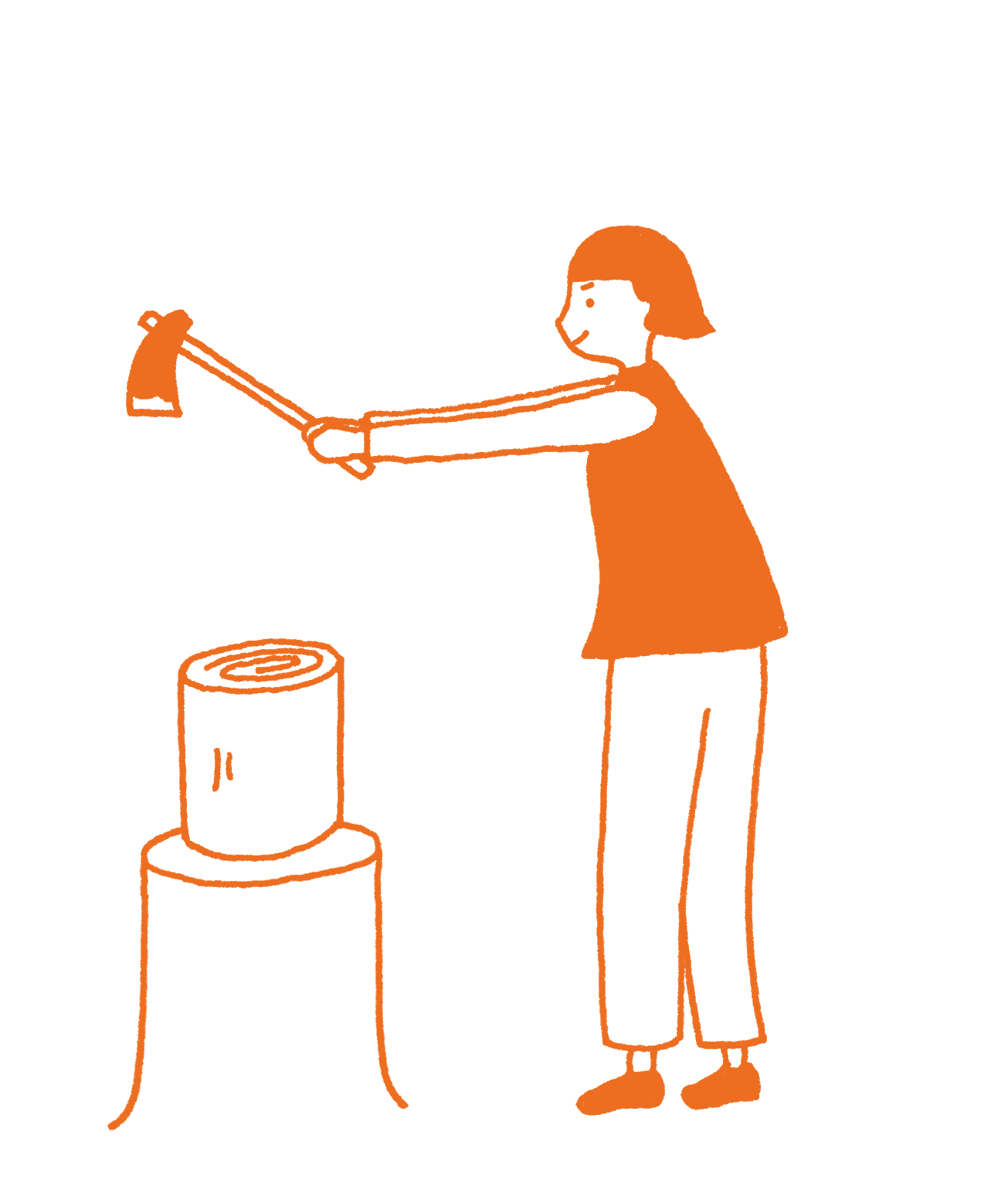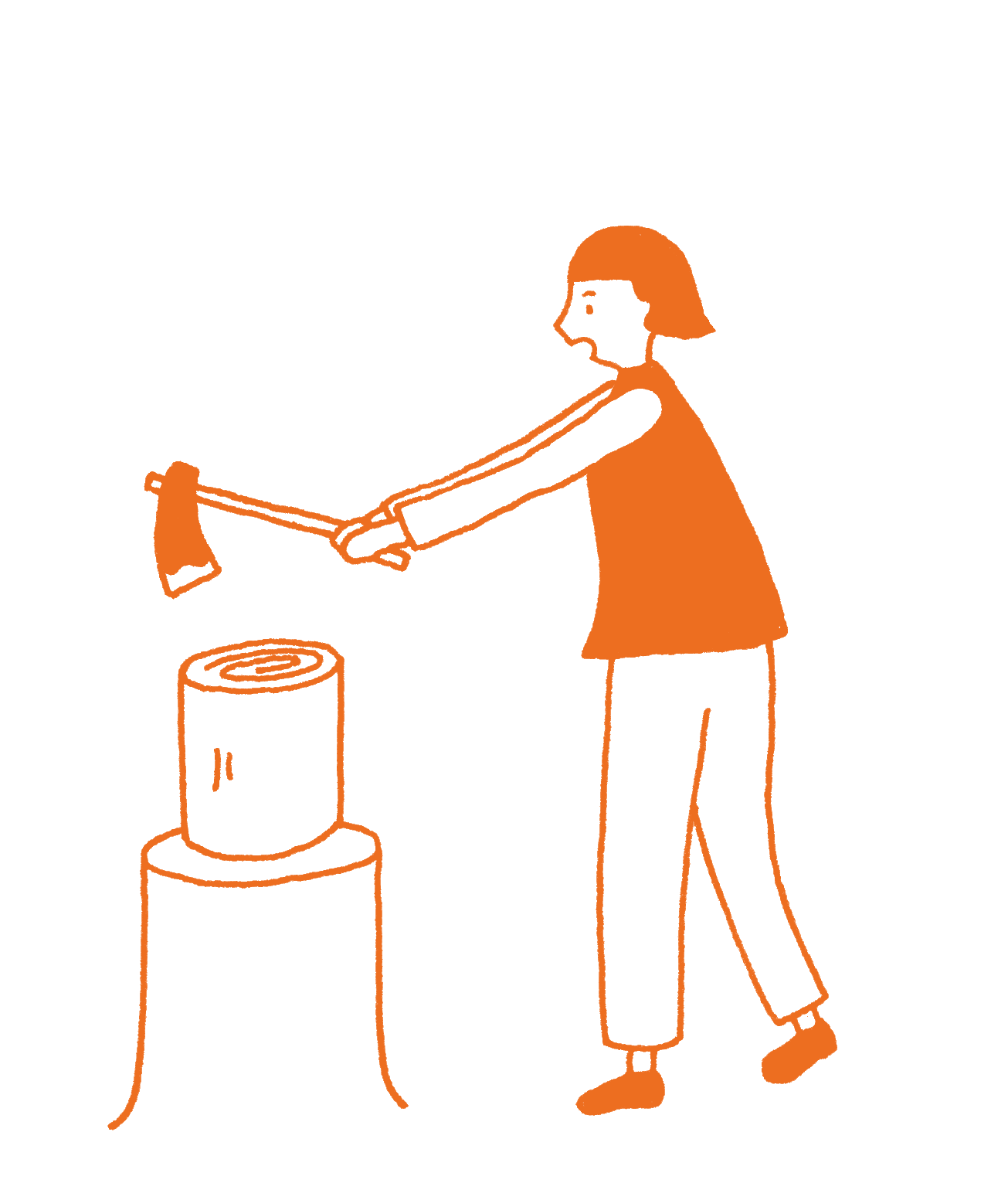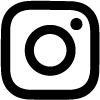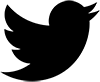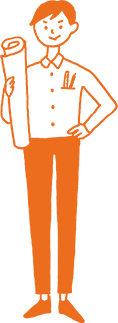山からやってくる木や土や竹で造られた「密厳堂」の一般参拝
「八事山 興正寺(やごとさん こうしょうじ)」は名古屋市中心部の南東に位置し、江戸時代に開かれた約300年の歴史がある真言宗のお寺です。
境内にはたくさんのお堂や仏像があり、中でも「五重塔」は江戸時代中期に建立されたもので国の重要文化財に指定されています。


この春、その興正寺の境内に、護摩を焚き祈願するお堂「密厳堂(みつごんどう)」が新たに竣工しました。
2025年5月に、寺院などの完成を祝う「落慶法会(らっけいほうえ)」が行われ、現在は一般参拝ができます。自然に還る建材を使って日本の伝統工法によって建てられた「密厳堂」の建物と、工事中に開催された「土壁塗り体験会」についてレポートします。
「興正寺 密厳堂」の特徴とは


「密厳堂」は、ご住職である西部法照(にしぶほうしょう)様の「日本人が大切にしてきた簡素の中に見出されるシンプルな美を大切にしたい」というご希望で、装飾を極力おさえたデザインになっています。
木材は木曽ヒノキを中心に、ほかにも岩手県産のアカマツなどの国産材が使用され、床は正方形の「敷瓦」を斜め45度に敷きつめる「四半敷」となっていて、壁は「土壁」を白漆喰で仕上げてあります。

今回、キノマチポイントとしてお伝えしたいのは、「興正寺 密厳堂」の工事で、地域の子ども会や大学生にむけて「土壁塗り体験会」を開催した点です。
日本の伝統的な建築技法で建造される木造の建物が、どのように造られるのか知ってもらおうと興正寺のご住職と工事担当者が企画。
今ではなかなか目にする機会のない、昔ながらの木組みや、竹小舞による土壁など、自然に還る材料からできる建物を、子どもたちや若い学生に伝えたいというご住職や工事担当者の想いが伝わってきます。土壁の仕上げに塗られた「白漆喰」も自然の材料であるサンゴ礁が堆積した石灰石からできています。

子どもたちに塗ってもらったのは、多くの参拝者が接するお堂の正面の壁です。実際の新築工事に参加することで生まれる、建物への親しみ、協働した時間や思い出が参加した人たちをつなげてくれます。愛着を育むことで、子どもたちに、自分たちが塗った壁をこれからも時々見に来てほしいというご住職の想いもあるそうです。
見て・触って・考える! 山や田んぼからやってきた自然の建材ご紹介

体験会はまずは「原材料とのふれあい」から始まりました。土で壁を造ることができるんだということを子供たちに知ってもらいます。
土壁とは、粘土に山砂や藁を混ぜて水で練ったものを塗り固めた壁のこと。密厳堂の土壁に使われた粘土と山砂と藁は、岐阜県多治見市や愛知県瀬戸市などからやってきました。
多治見市といえば「美濃焼」で有名な陶磁器の産地として知られています。美濃焼についてはキノマチニュース「ラーメンどんぶり展」でも紹介しました。
土壁の材料は水を入れて混ぜ合わせた後、「練り置き」といって粘りが出るまでしばらく置きます。この「練り置き」によって、乾燥や収縮を抑えひび割れを防止する効果が生まれます。

次に密厳堂の土壁を施工された左官職人天池さんによる「竹割りの実演」。

土壁の下地となるのは、細い竹を格子状に編み込んだもので「竹小舞(たけこまい)」と呼ばれます。今回の竹は岐阜市の山からやってきました。
「寒伐り(かんぎり)」といって、竹の水分が少なくなる冬の寒い時期に伐採することで、竹の締まりが良くなり、加工しやすく、腐りにくくなるとされています。
体験会では、実際にこの竹で組まれた壁に土が塗られていきました。

見て・触って・考える! 日本の伝統的な建物の木組みの技法
密厳堂はご住職の想いにより、日本の伝統工法による木造建築として、社寺建築を専門とする「白鳳社寺」の宮大工さんの手によって建てられています。子どもたちは「伝統的な仕口3D模型」にふれたり、「木組みコースター作り」を通して木造建築の伝統的な技法についても学びました。


そして今、土壁は「環境にも人にもやさしい建材」という観点からその機能も見直されています。土壁には「調湿性、断熱性、防火性」というすぐれた3つの特徴があります。
まず、湿度が高い時は空気中の水分を吸収し、低い時は水分を放出してくれる調湿性に加え、熱や冷気を逃がしにくい断熱性もあるため、酒蔵などに活用されてきました。
さらに、土は燃えにくいものなので防火性にもすぐれていて、昔の大切なものをしまっておくための蔵などにも土壁が使われていました。
建築基準法でも、2022年に不燃材料として正式に追加され、厚さ10ミリの壁土が厚さ12ミリの石こうボードと同等の不燃材料として認められるようになっています。
子どもたちや地域の人が、実際に材料の土や竹に触れるところからはじまった「土壁塗り体験会」。そこから木造の建物がどうやって造られていくのかまで体験できる機会を通して、山とまちがつながっていく芽が育っていく。このような取り組みが色々な場所で広がっていくことを願います。
子どもたちが塗った壁がこれから長い時間、お寺を支えてくれます。地域の人たちに木や土の建物づくりに参加してもらうことで、山との距離がぐっと近くなった「興正寺 密厳堂」新築工事。まちで木の循環を感じられる興正寺に、ぜひ足を運んでみてください。


Text:野村裕子
■情報
「八事山 興正寺 密厳堂」
場所:愛知県名古屋市昭和区八事本町78
八事山 興正寺 HP:https://www.koushoji.or.jp