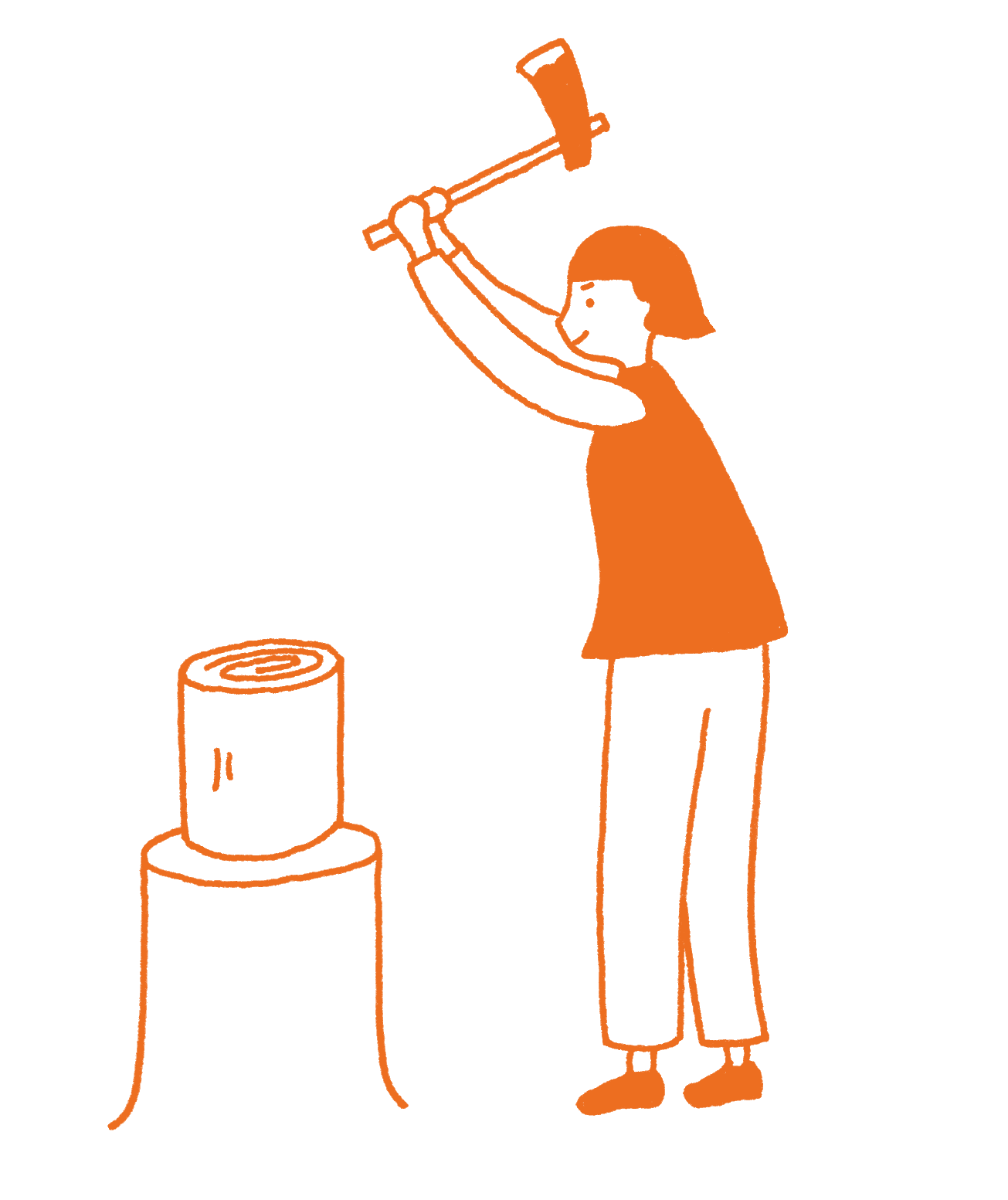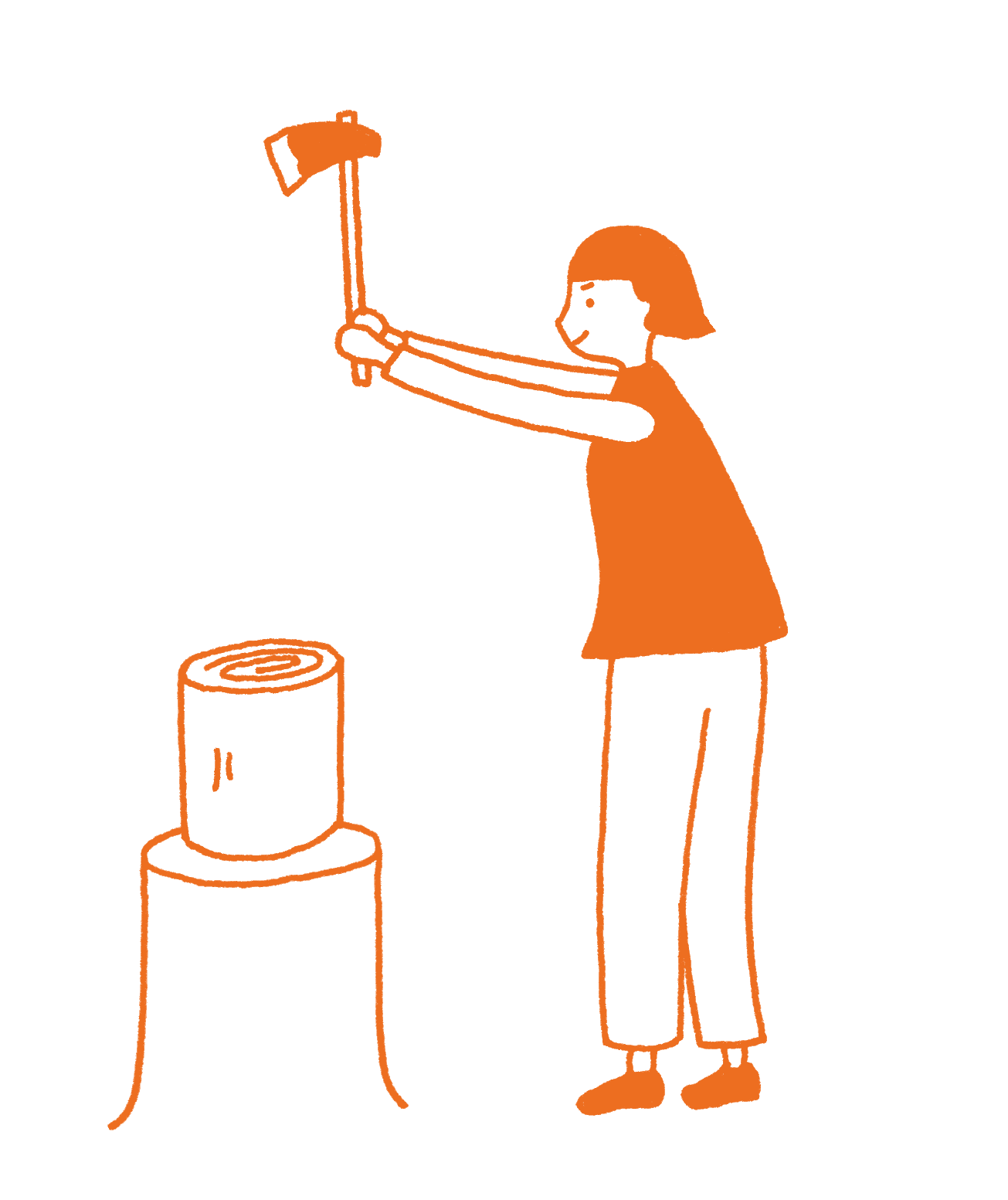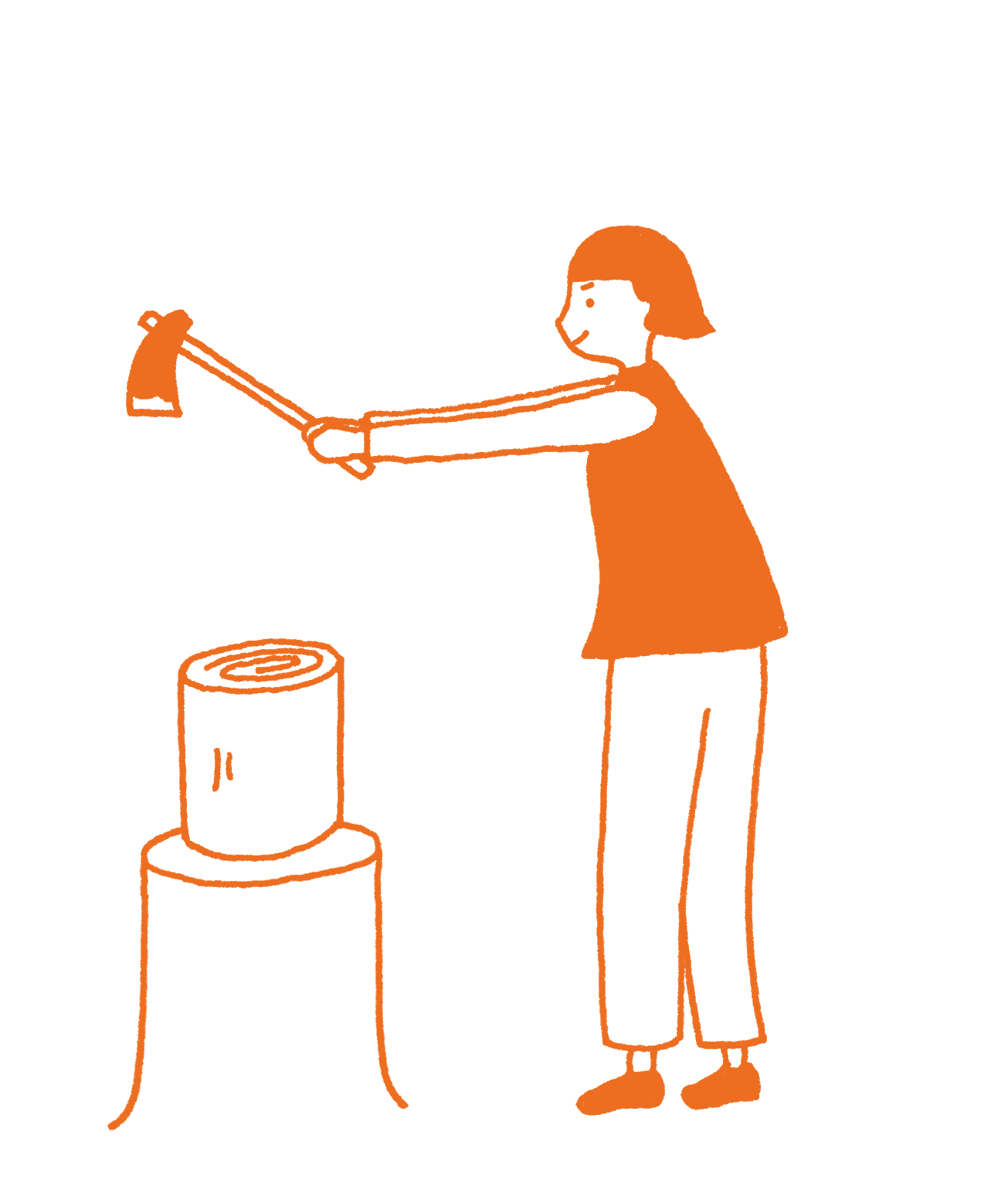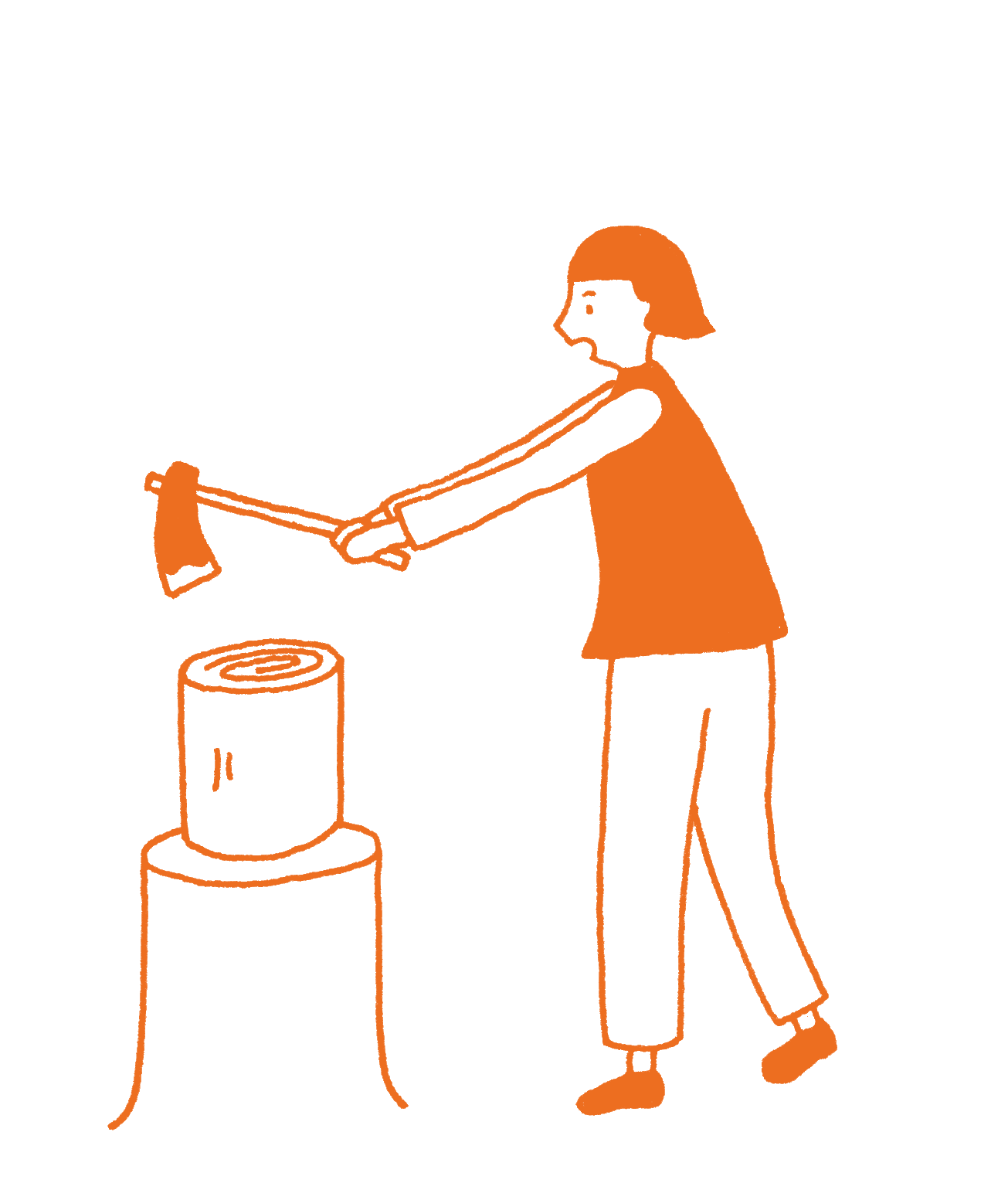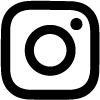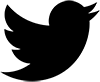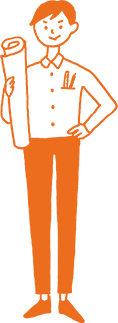三重県熊野市「株式会社nojimoku」へ
皆様、こんにちは。今回のコラムは連載第2弾「中編」です。 前回はキノマチミートアップ、前半2日間の奈良県から和歌山県での訪問先についてお伝えしました。
最終日の3日目は、主に「川中」である「製材所」を巡ります。
三重県熊野市では、nojimokuさんから新設されたばかりのモダンで小粋なショールーム「木挽座」に案内されたのが、まず最初の驚きでした。プロダクトを売るだけでなく、自分達のことを知ってもらう、その重要性に気づいて建てられたとのこと。それを実際に実現する実行力に敬服します。
<木挽座 by nojimoku WEBサイト: https://nojimoku.jp/2645/ >

このショールームで社長の野地伸卓(のじのぶたか)さんからまずプレゼンを受けました。このプレゼンがまた上手い!最初に「皆さん、山から木を伐り出す人を木樵、まちで木を使って建物をつくる人を大工、と呼びますが、私たちのような製材する人を何と呼ぶか、知ってますか?」という問いかけから始まります。
なかなか答えられないと「そうです、私達はどんな職業で何をしているのか、言語化されていないのが問題でした」と続く。

最初の質問「製材する人を何と呼ぶか?」の答えは「木挽き職人」。では、その木挽き職人は何をしているか、というと単に原木から機械で自動的に板材を切り出してだけではなく、その基盤にあるのは技術力、すなわち目利きとしての丸太の選定、歩留まりを考慮した木どりの能力です。
ここで、原木の質とその販売価格は木の「節」の大小と強く関わってくる。nojimokuさんはその歩留まりを考慮した木どりを理解するためにセーザイ(製材)ゲームまで作ってしまったんです!僕たちも木挽き職人になったつもりで、セーザイゲームに没頭してしまいました。

余談ですが、このゲームはウッドデザイン協会主催のウッドデザイン賞で2023年林野庁長官賞を受賞しています。
<ウッドデザイン賞HP:https://www.wooddesign.jp/db/production/1873/>
もともと、和室を設える吉野桧、尾鷲桧などの高級材を扱う製材所でありながら、PR拠点「木挽座」を建設してそこで関係者と対話したり、自分達の仕事を認知、理解してもらうためにゲームまで作って啓蒙活動にも精を出す、これはキノマチに関わる人々の間でここ数年に始まり、広がりを見せる新しい気運と言えます。
すなわち、地方、地方の小さなコミュニティが確実に特徴ある新しい活動を開始し、その輪が広がりを見せている感覚があります。
視察ではこの後、さらに北に向かって2か所の製材所を巡ることになります。
三重県多気郡「武田製材有限会社」
一人一人の特別な注文やニーズに応えようと広葉樹中心に多様な部材を提供しようとする「武田製材」。
<武田製材 WEBサイト:https://beaver-house.com/>
ここで扱われているのはチェンバロなどの楽器、数珠・アクセサリーなどの工芸作家用、あるいはソロバン玉、カンナ台などの原木で、ちょっと、というか、かなりマニアックな材を扱う製材所で、そこに一歩、足を踏み入れると私設の特注品銘木市場といった感があります。

社長の武田誠さん、サービス精神が満載でその場でいろいろな木を製材し、手に取って見せてくれました。例えば弓の中間部材にも使われる「ハゼ」。木肌から鮮やかな黄色い絵具が染み出てくるようで、その見事なこと! 武田さんによると「木は製材直後が一番、美しい」。



続いては、今やなかなかお目にかかることが少ない、消耗してすり減った帯鋸(おびのこ)などの刃を研ぐ「目立て」の実演。鉄と鉄の格闘のような火花が散っていました。
さらに武田さん曰く、3大ポイズンウッド、アセビ、シキミ、キョウチクトウに関わる体験談など、皆、その豊富な話題に引き込まれていました。
話を聞くキノマチメンバーの目は輝いていましたが語る方の武田社長はそれにも増して楽しそうでした。そして最後の訪問地、愛知県に向かいます。
最終訪問地。愛知県弥富市「株式会社ヤトミ製材」
株式会社ヤトミ製材は国産材の巨木に加えてアラスカ、アフリカ、東南アジア、ヨーロッパなど世界中からの輸入材を扱っています。特にアラスカからは樹齢900年ともいわれるような巨大なスプルースを輸入し、貯木場での保管を経て、製材し、製品を流通させています。
<ヤトミ製材WEBサイト:https://yatomiseizai.com/>
ようやくその最後の訪問地のヤトミ製材に辿り着きました。
実はヤトミ製材の専務取締役の加藤圭一郎さんは、和歌山県研究林の行程からこのミートアップに参加してくれていたんです。ヤトミ製材さんは愛知県にあり、名古屋港に運ばれてきた木材を水中乾燥するために貯木場で水没させ、必要な時期に陸揚げして製材する工程が基本になっているようです。

resize-1024x768.jpg)
水中乾燥とは、木材を水中に沈めることで水が抜けやすくなるとの性質を利用したものです。ここでもヤトミ製材の加藤徳次郎社長が直々に、直径1400ミリもあるアラスカスプルースを眼前で挽いてくれました。
何でもアラスカ産のこんな巨木はほとんどフランスやドイツに流通していて日本にはその1パーセント 程度しか入ってこない、というレアものです。
先の武田製材さんが「木は製材直後が一番美しい」と言った話はお伝えしましたが、今回のスプルースも断面が美しく、社長から「この大きなスプルースは思ったとおりの良木で評価は90点、自分自身、木の目利きとして満足している。」とのコメントがありました。

確かに切ってみないとわからない木の質を外観から見抜くのはよほどの経験、力量がないと無理ですよね。
僕の心に残ったのは大木を製材している時に社長が口にした「こうやって毎日、木を製材しているが、木がモノに見えてしまわないように、日々、気を付けている」の一言でした。
扱っている、生きている木への愛情が失われると心が通うようないい仕事に繋がらないと自戒の声を聞いたような瞬間でした。実際、木と対面、対話しているのですね。


(【後編:全体総括】に続く)
前回のコラム

(語り手)キノマチウェブ編集長
樫村俊也 Toshiya Kashimura
東京都出身。一級建築士。技術士(建設部門、総合技術監理部門)。1983年竹中工務店入社。1984年より東京本店設計部にて50件以上の建築プロジェクト及び技術開発に関与。2014年設計本部設計企画部長、2015年広報部長、2019年経営企画室専門役、2020年木造・木質建築推進本部専門役を兼務。