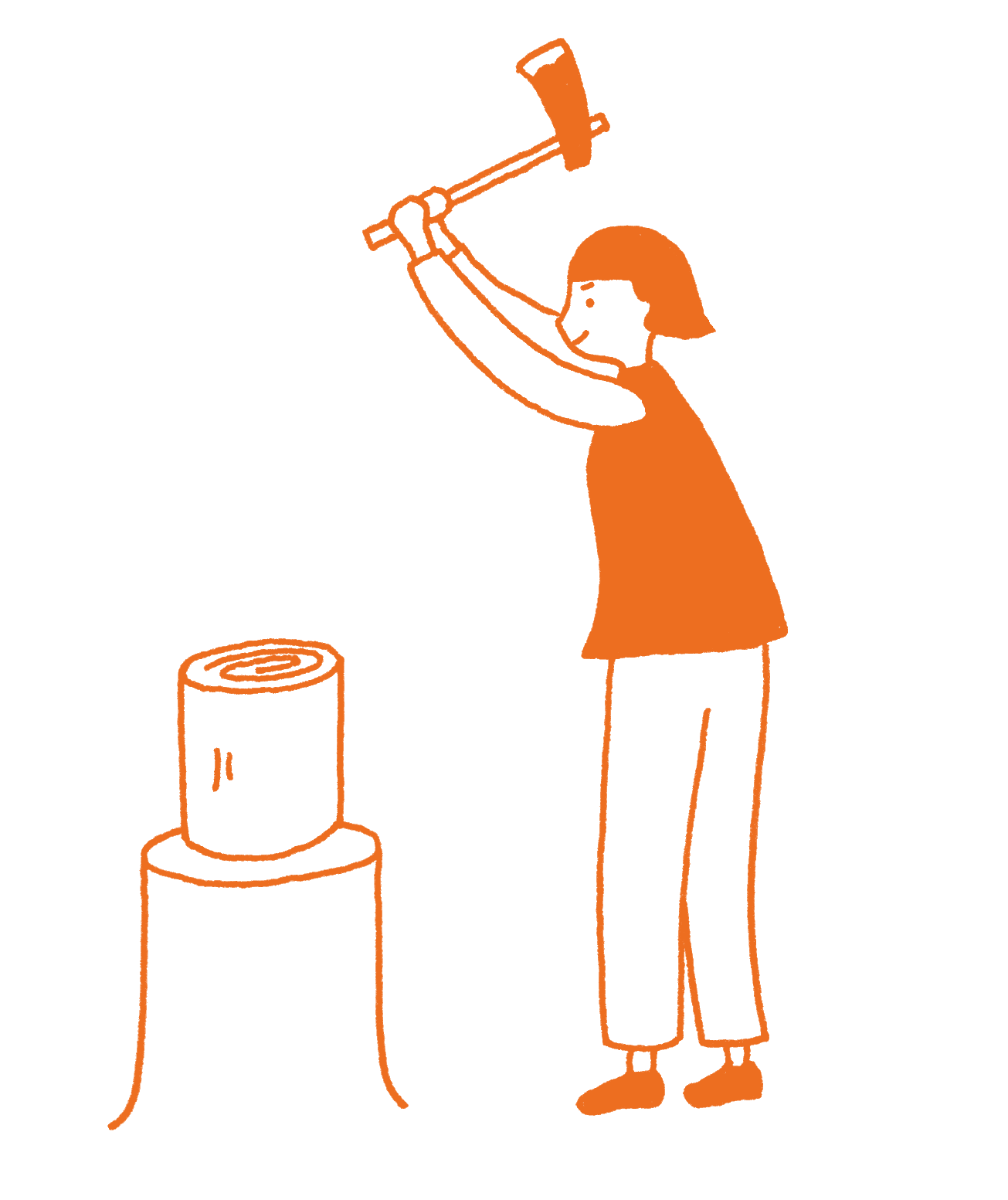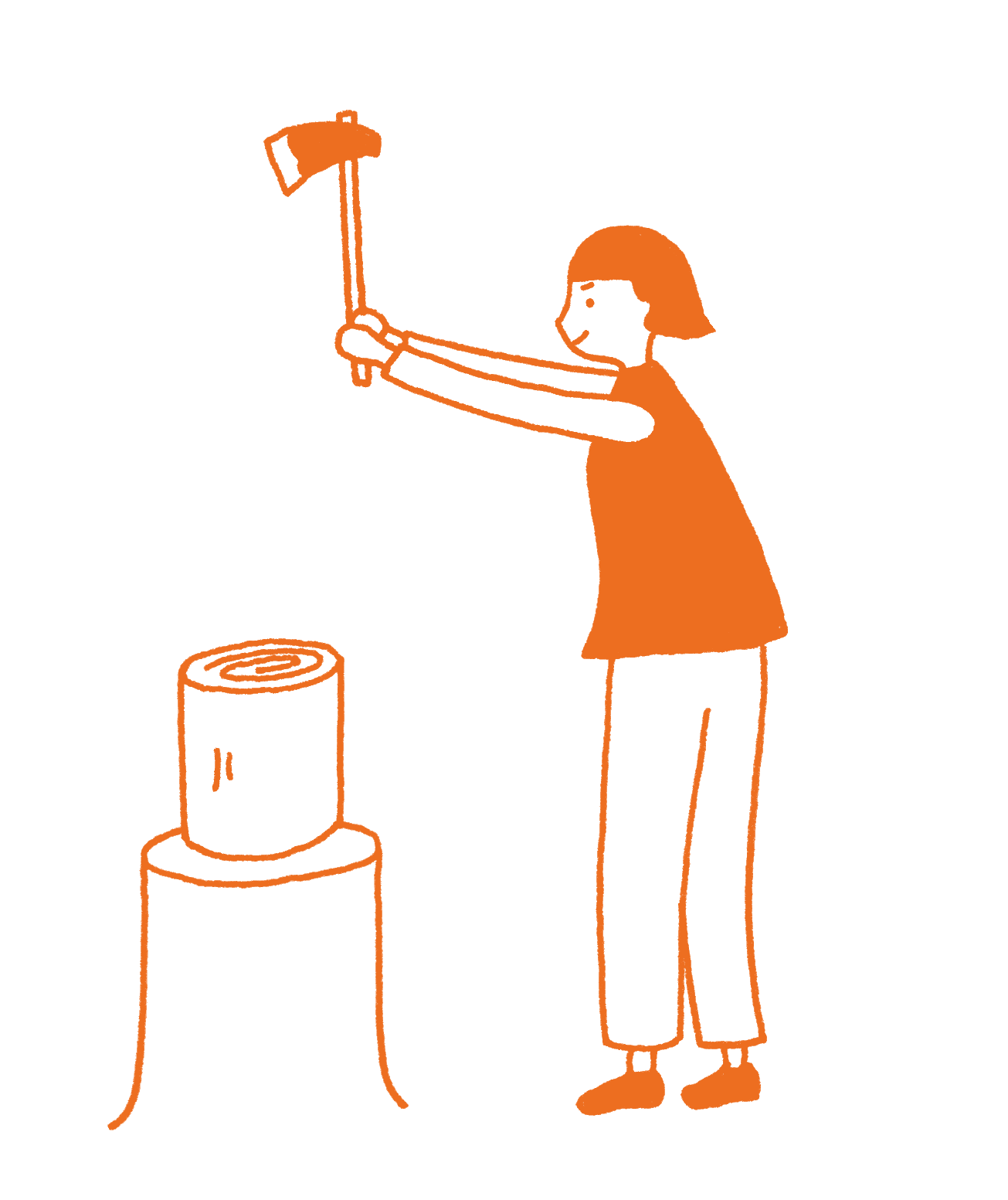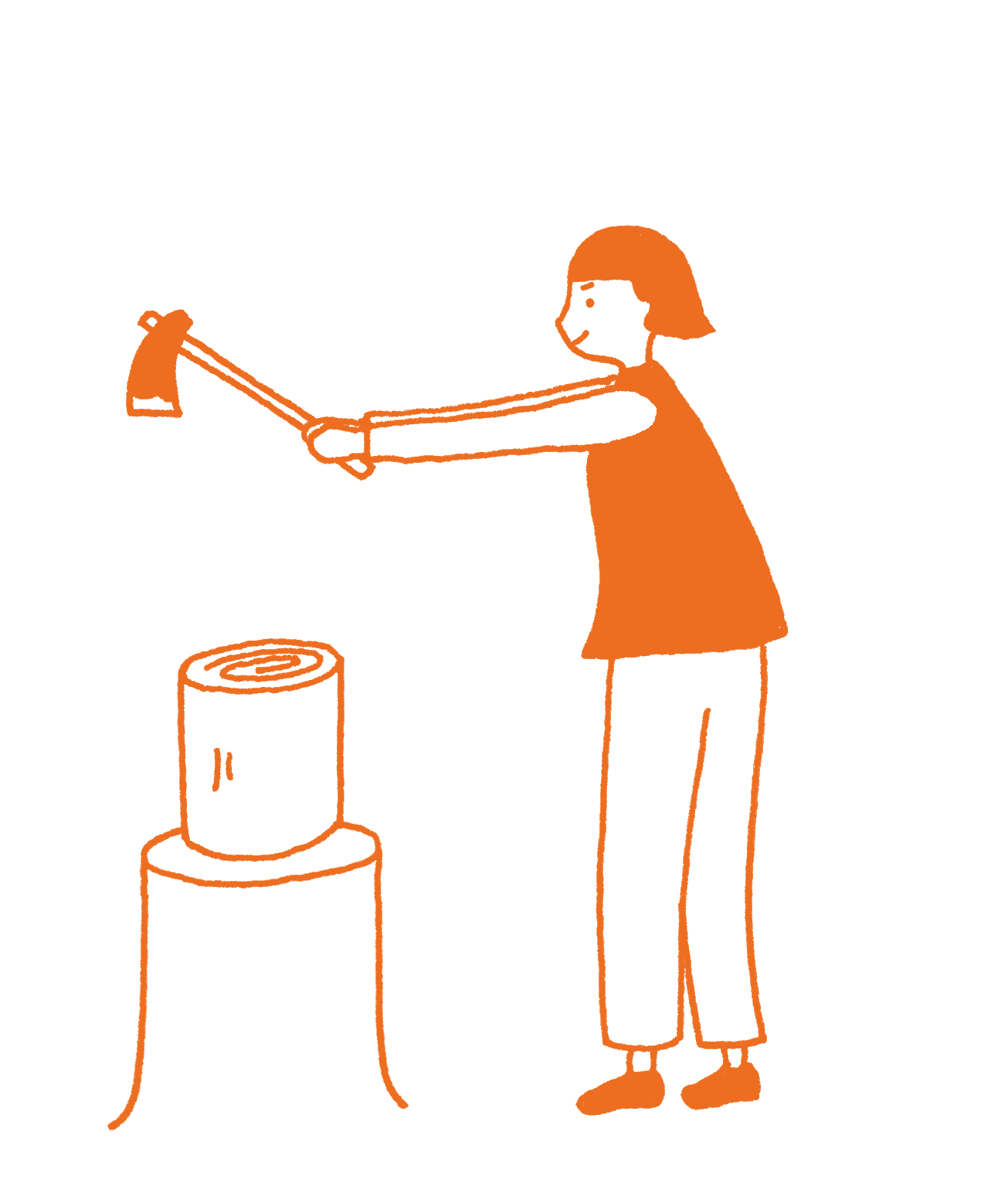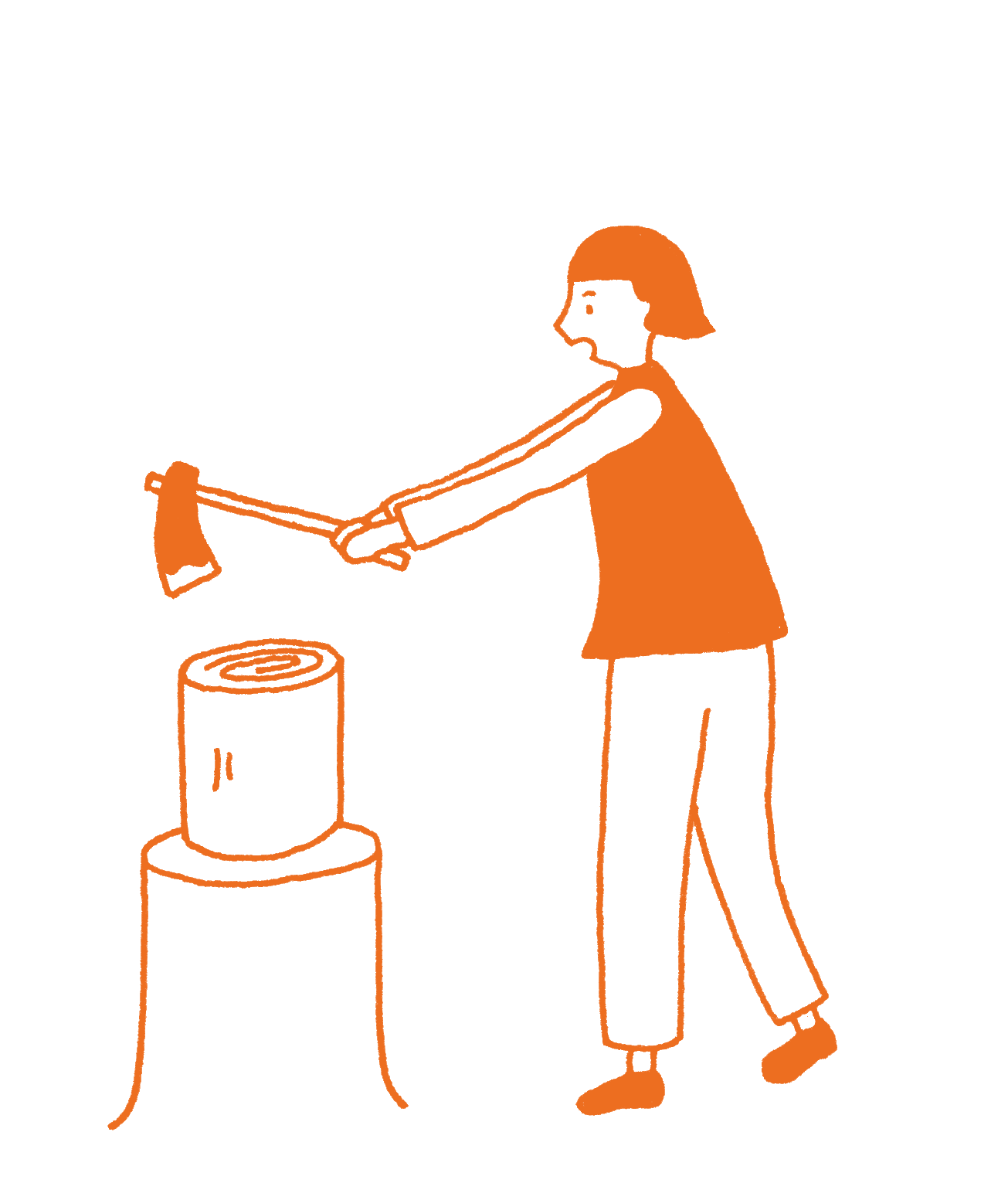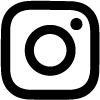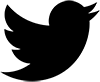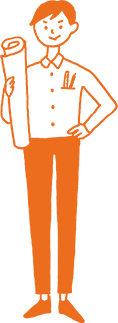「建築主の理解がすごく深まってきていることを肌で感じています」
木造建築を取り巻く環境の変化について、竹中工務店木造・木質建築推進本部の花井厚周さんは、そう語りはじめます。
キノマチプロジェクトがスタートして5年。以前と比べて、木の特性や良さを理解した上で木造建築を発注する建築主が増え、特に近年は、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが加速する中で、木材の持つCO2固定効果や再生可能な資源として木造は確実に新時代を迎えています。
そんな潮流のなか、竹中工務店は『森林グランドサイクル』の実践者として新たなステージに踏み出そうとしています。
構造設計者として、木造・木質建築推進本部長として木造建築の最前線を走り続けてきた花井さんに、木造建築の現在地と未来について伺いました。

花井厚周 Atsunari Hanai
株式会社竹中工務店 木造・木質建築推進本部長。1994年竹中工務店入社。構造設計者として、日本国内初となる耐火木造の大型商業施設「サウスウッド」の構造設計を手掛ける。現在は木造・木質建築推進本部長として『燃エンウッド』から適材適所の木質化まで幅広い技術提案で木造建築の可能性を広げている。
2025年、木造建築の現在位置を語る
ーー 花井さんから見て、現在の木造木質の潮流、現代社会において木造建築がどのような立ち位置にいるのか伺いたいです。
花井さん「私はもともと構造設計者です。耐火木造を実際に設計することにも携わった者として、いまは建築主の理解がすごく深まってきていることを感じています。
ほんの数年前は、『木は傷つくんじゃないか』『経年変化があるんじゃないか』など、建築主の懸念から説明していたのが、今、皆さん木の性質を分かった上で発注するじゃないですか。理解が深まったことで木造そのものも普及してきました。
しかし、4階建て以上の非住宅建物の木造化など、まだまだこれからだと考えています。その原因はやはりコストでしょうか。まだ課題がありますね」
ーー大阪・関西万博の『大屋根リング』などは、本当に革新的で大規模な木造でした。日本を代表する建物をつくるとき、木造を選択しているにもかかわらず、一般的には中高層木造というチョイスがまだまだ浸透していない、と乖離を感じます。
花井さん「私、先日、大阪・関西万博で、建物に自国のCLT(直交集成板)パネルと伝統工芸であるボヘミアンガラスを全面採用した『チェコ館』を見に行ったんです。
欧州を拠点とする建築設計事務所アプロポス・アーキテクツが手掛けたものですが、『日本の木造や建築の基準が厳しくて大変だった』と伺いました。やはり、木造建築を難しくしているひとつは、厳格と言われている火災安全性に関わる建築基準法や消防法などの法規制です。
木造が超えるべきハードルとして、付加価値の認識や評価はだいぶ進んできたと感じます。あとは、もう少し木が使いやすい法律になるとありがたいなと思っています。加えて、コストの問題も残ります」
ーー 木造のコストは、何にいちばんお金がかかるのでしょうか。人件費、材料費、いろいろあると思いますが。
花井さん「一番金額がかかってるなと思うのが、耐火技術です。大規模木造建築は、現在、その建物のためにイチから開発していますから。規格化した部材を組み合わせて、木造をつくっていくことも今後必要だと思います。
『木造は高い』と言われますが、今までと同じやり方や考え方で、建設費だけを見ると、木造はやはり高いんです。
たとえば、木造にし、さらにプレハブ化することで、工期が短縮され、資金回収が早まります。違った目線のスパンで見ると、事業計画的にはコスパは悪くない。
建設費だけ切り取って見ず、さまざまな尺度で見ていけば、もっと木造が普及するのかなってちょっと思ってはいるんですけど」
ーー 木造の課題にチャレンジした竹中の木造建築はありますか?
花井さん「頑張ったのは『立命館アジア太平洋大学(APU)』です。APUは当時の法律を非常にうまく咀嚼して、燃えない耐火部材のところ、耐火のゾーンと準耐火のゾーンを分けて設計できたことが素晴らしい。あれぐらいの大規模な木造建築で適材適所を組み合わせてできたというのは、いいなと思います」
あとは北海道の『北海道地区FMセンター』あたりも新しい取り組みだと感じます。北海道という土地柄に寄り添ったものづくりです」

花井さん「他社で印象深い建築は、稲山正弘先生が構造を手掛けた『AQ Group本社ビル』。先生のポリシーがあって一般流通材で8階建て純木造をつくられていました。あんなところまで行けたら、と思いました」
ーー 花井さんが竹中工務店に入社されたときと今では、木造技術はどう変わりましたか。
花井さん「私が竹中工務店に入社したときの木造建築の立ち位置は「伝統建築」でしかあり得なかったです。法改正で木造の大型建築物がつくれるようになり、サウスウッドから潮目が変わってきました。加速したというか」
ーー その時、実際に設計した時の悩みと今の悩みって変わらないですか。
花井さん「つい数年前まで、中高層木造建築の構造技術といえば耐火集成材『燃エンウッド』一辺倒でしたが、今は、様々なニーズの木造を実現するいろんな技術がありますから、お客様のご要望に合わせた木質空間を提供できるようになりました。
当社は、今年度、日本橋で『(仮称)日本橋本町一丁目3番計画』として国内最高層の木造ビル(地上18階・高さ84メートル)を手掛けています」

花井さん「竹中工務店の中高層木造建築が進化してきたのは、「数年後に国内最高層の木造ビルをつくる!」というマイルストーンに合わせて技術開発を着実に進めてきたこと。
5年、10年先、こうあったらいいなというイメージを持ち、それを実現するためにはどういう技術が必要なのかをみんなで話し合いながら開発してきたのが、現在の木造新時代につながっているかと思います」
ーー 非住宅かつ、大きな木造建築『(仮称)日本橋本町一丁目3番計画』が2026年度に完成します。竹中工務店は、今後もこのような大規模な木造建築の建設を積極的に進めたいのでしょうか。
花井さん「リーディングカンパニーとして、技術力の優位性を保ちたいなと思う部分です。最先端のものはやっておきたい。ただ、超高層のものは数年に1度あるかないかの建築です。
たとえば、10階建て1万平米程度の木造建築が当社の主戦場なんじゃないかなと考えます。都市部に限っては、ですが」
ーー 都市部以外についてはどのようにお考えですか。
花井さん「最近思っているのですが、地方でいわゆる『消滅自治体』と呼ばれるまちが多々あります。当事者のまちの方にお話を伺うと、『俺たちの街に10階建て以上の建物ないんだよ』といいます。
あるのは人が住まなくなったようなビルなど空き家で、そこに人が来ない。集う場のない若者は都市部に出て行ってしまう。
私は、地方の街にはストックを有効に使えるような、価値向上につながる技術も必要だと考えています。ストックを活用して人を呼ぶことができる技術が、人口減少していくなかで必要です。そこに木造木質の技術が必要になるではないかと」
ーー ちなみに花井さんが竹中の木造建築で一番すきなものはなんですか?
花井さん「自分が設計したもの!って言いたいんですけど、私は『水戸市民会館』が好きです。『燃エンウッド』はいつも「太い」「使い勝手が悪い」と揶揄されることも多々ありましたが、伊東豊雄先生が本当に素晴らしく設計されたなと思いました。先生、すごいなと感じます。
先日も訪れました。何が良いかって、使ってる人たちがすごく大事にしてて溶け込んでるんですよ。子供たちはここで勉強してたりする。自然に大人も、高校生も、子供たちもいて。
そういう空間、建物が地域の人に愛されている建築っていいなって思いました。みんなから好かれてるというところも、この建築が好きな理由です」

竹中工務店が森に向き合う意味とは
ーー竹中工務店は森林グランドサイクルを進めるために森と向き合おうとしています。
花井さん「『森林グランドサイクル』を提唱するなかで、当社も、自分たちで森を活用していくための検討を始めています。もともと、ご縁があった長野県塩尻市で木曽の『森林グランドサイクル』を自分たちで回していく試みです。
森からカラマツなど原木を搬出して、その木をできるだけ無駄なく使おうと、大径木は『燃エンウッド』に。小径木も新たな付加価値の高い使い道はないか、と自分たちで考え、実践できないかと。それで、建築コストが下がれば、木造建築に立ちはだかるハードルのひとつをクリアできる可能性があります」
ーー 川上側に自分たちも関わる、ということを、花井さん自身はどう思われていますか?
花井さん「私は、比較的フランクに考えてました。たとえば、森、いっぱい買って持てばいいじゃないって(笑)。一方で、いろいろ知っていくと、とても気軽には森は所有できませんが、将来的には当社も何らかの形で森を持つ必要があると考えています。
提唱してきた『森林グランドサイクル』は、いまのままではスムーズに巡らないのではないかという議論も社内でありました。
木材産業の川下である竹中工務店は、川上・川中・川下ステークホルダーとつながり、『森林グランドサイクル』を回していこうという立場から、自身が川上・川中になり、『森林グランドサイクル』を主体的に回すチャレンジを進めていこうと思っています。

ーー 竹中工務店は、ものづくりにおいて「リジェネラティブ」に挑戦すると伺いました。建物をつくる上で、この挑戦をしていくことは木造・木質建築が深く関わっていくと考えます。
花井さん「私達がリードしていく分野ですね。木を使うことはサステナブルだけでなく、社会的価値を生み出していくことにつながります。炭素を固定するだけでなく、環境にプラスの影響を与えていく。
例えば、森を育てることで生物多様性を回復させたり、地域の林業を活性化させたり、建物そのものが周辺環境を再生していく力を持つ。そういう『再生する建築』は木造だからこそ実現できると考えています」
ーー キノマチウェブについて、印象に残っている記事ってありますか?
花井さん「『木材デューデリジェンス』は、その取り組みそのものも、ずっと気になってまして。日本では、デューデリジェンスに関わる費用について支払う発想がそもそもない。対価を払わなくちゃいけないでしょって思ってるのに。
岩永さんの記事が特にふむふむと思いました。私も、あれを読んで『なるほど』と理解が深まりました」
ーー 木造木質や木に関する、「いつか当たり前になる未来」を、キノマチウェブではお伝えするようにしています。
花井さん「大会議は昨年もよかったですね。今年は少しクローズドに長野県・奈良井でやろうという話を聞き及んでいます。今日お話したように、課題もあれば希望もある。
だからこそ、今は大きな過渡期にあると感じます。木造や木質化の可能性は、技術や素材の進化に加え、関わる人々の熱意やネットワークによってさらに広がっていきます。現場での試行錯誤や制度への働きかけが、次のステージを切り拓く原動力になるのかなと思います」
木造建築への理解は確実に深まってきています。しかし、いまある課題を乗り越え、さらなる普及を目指すには、まだやるべきことがあります。そのなかで竹中工務店が自ら木材産業の川上や川中にも取り組もうとしていることは、木造建築の未来にとって大きな意味を持つのではないでしょうか。
花井さんのお話から、木造建築が特別なものではなく、当たり前の選択肢として定着する未来への期待が高まりました。木に関わる人たちの粘り強い挑戦と、分野や地域を越えて結びつく思いと、そのネットワークこそが「いつか当たり前になる未来」をかたちづくるのです。
Text:アサイアサミ(ココホレジャパン)
花井さん登壇のイベント